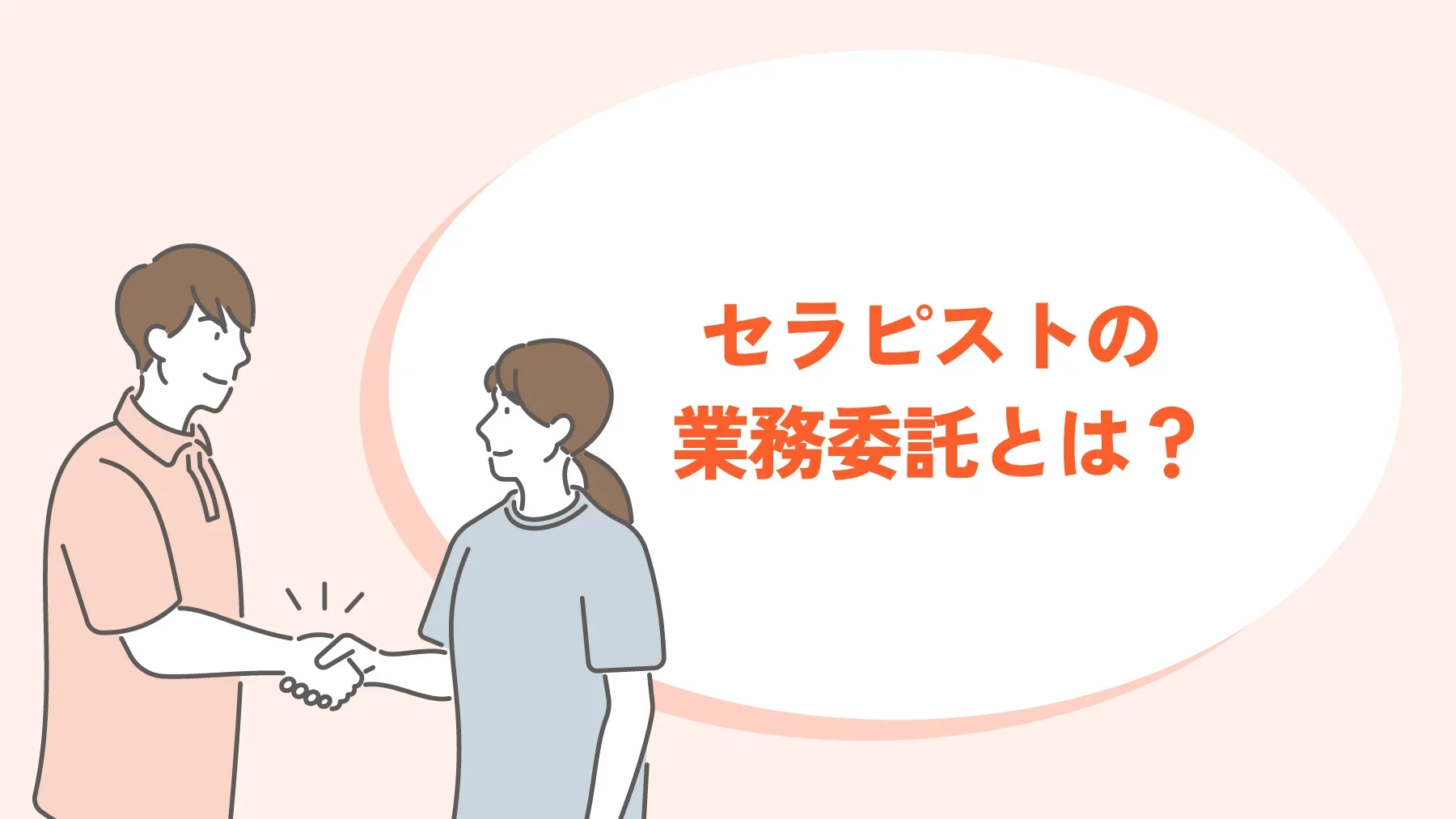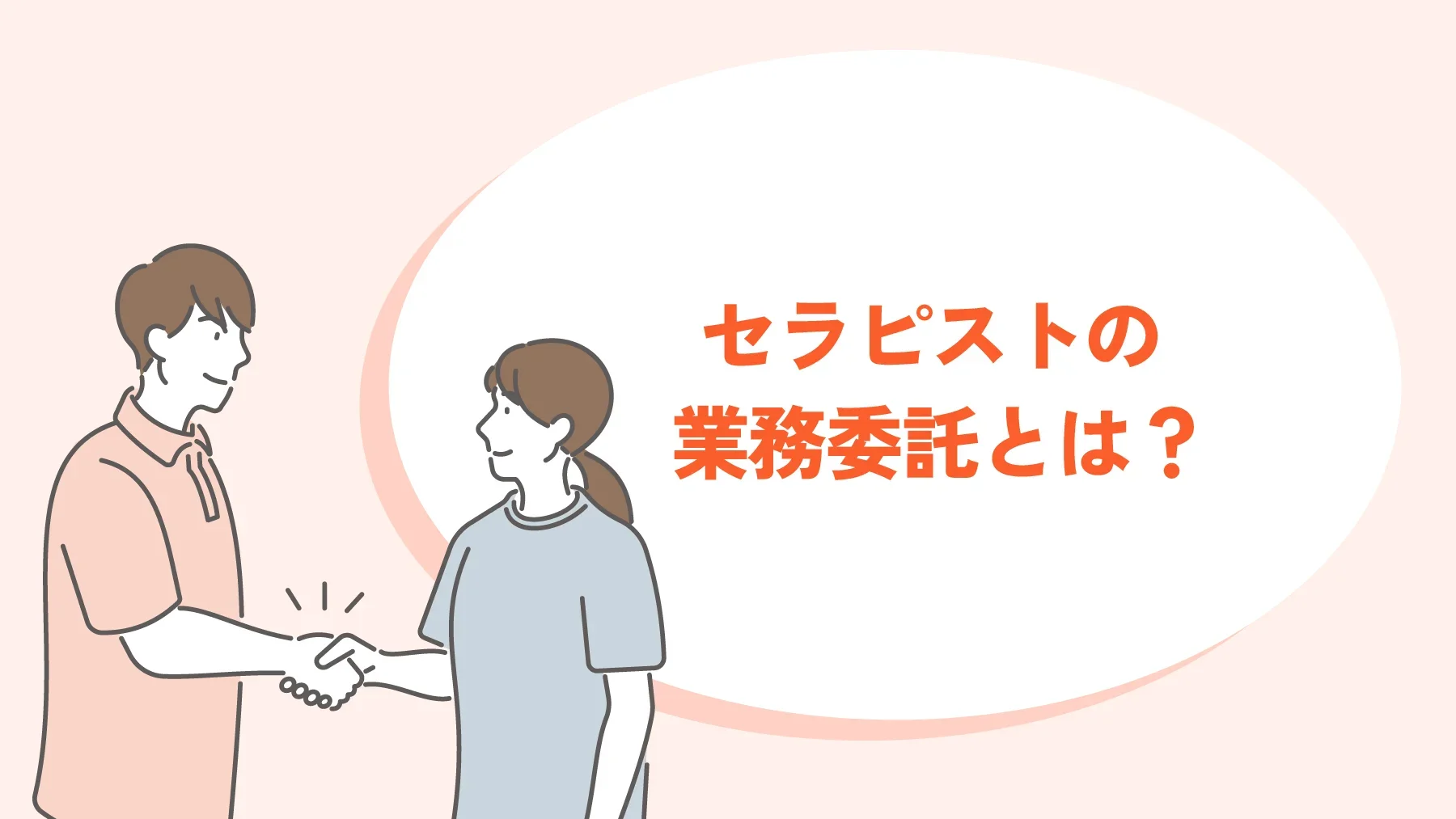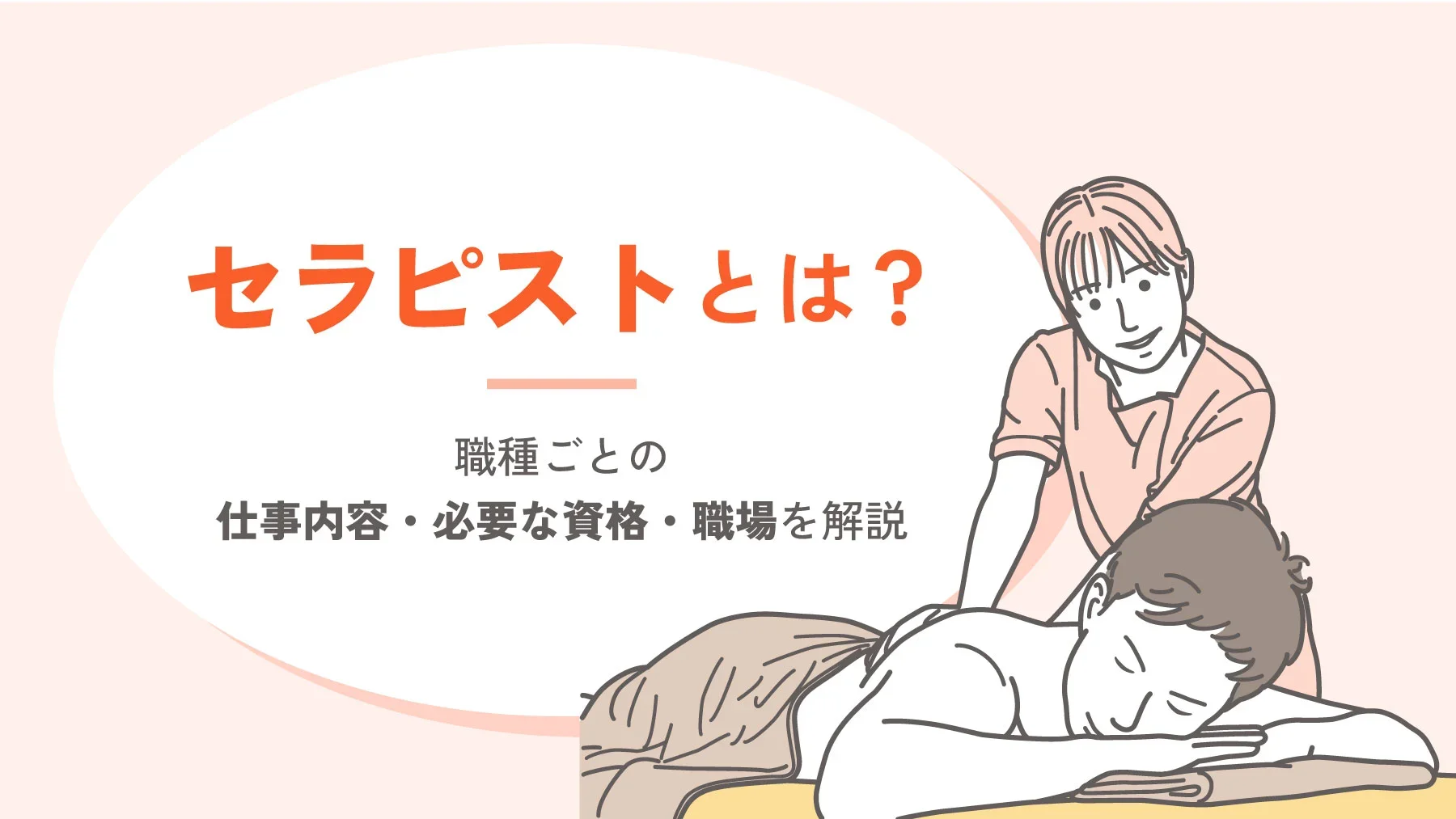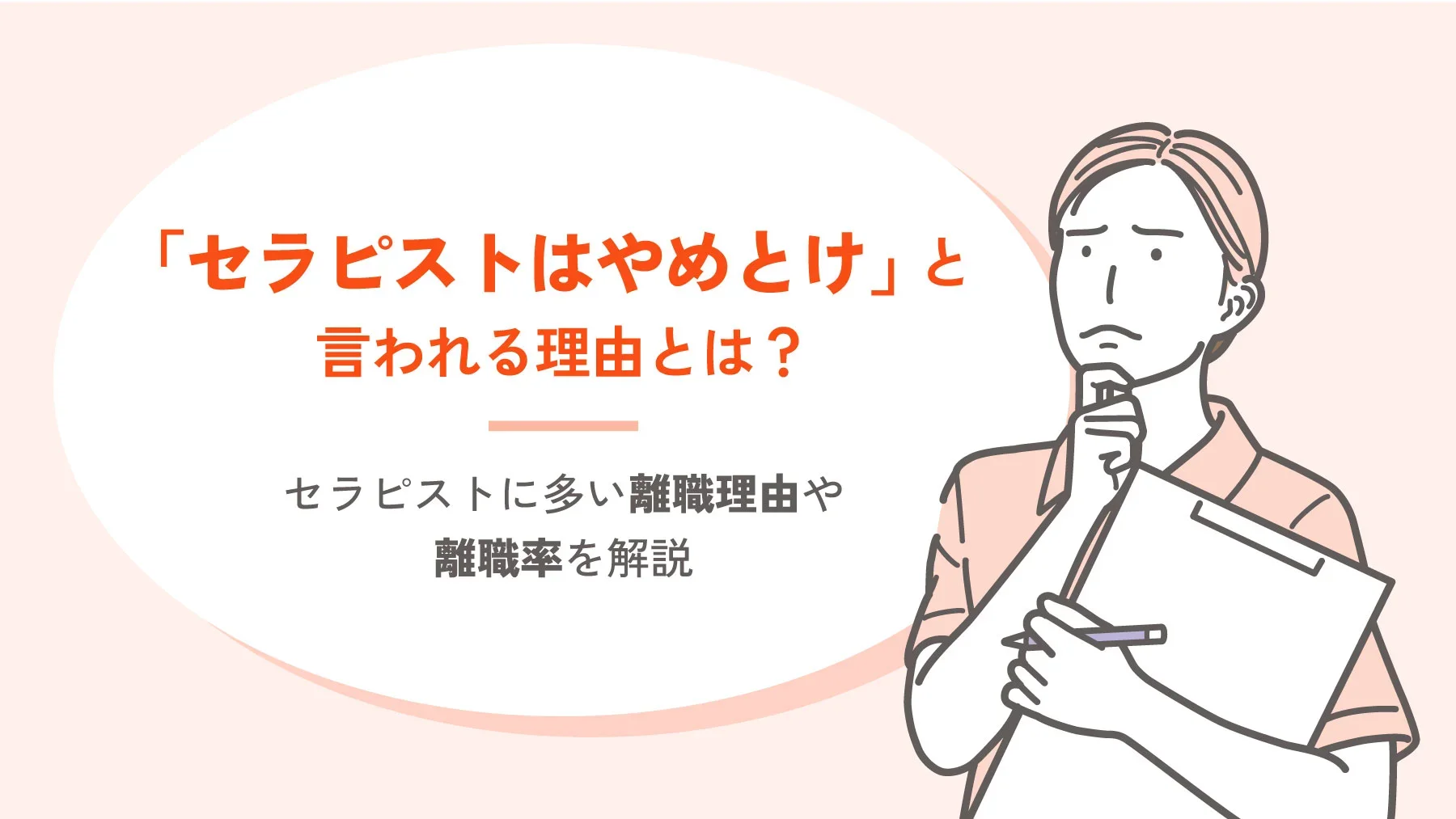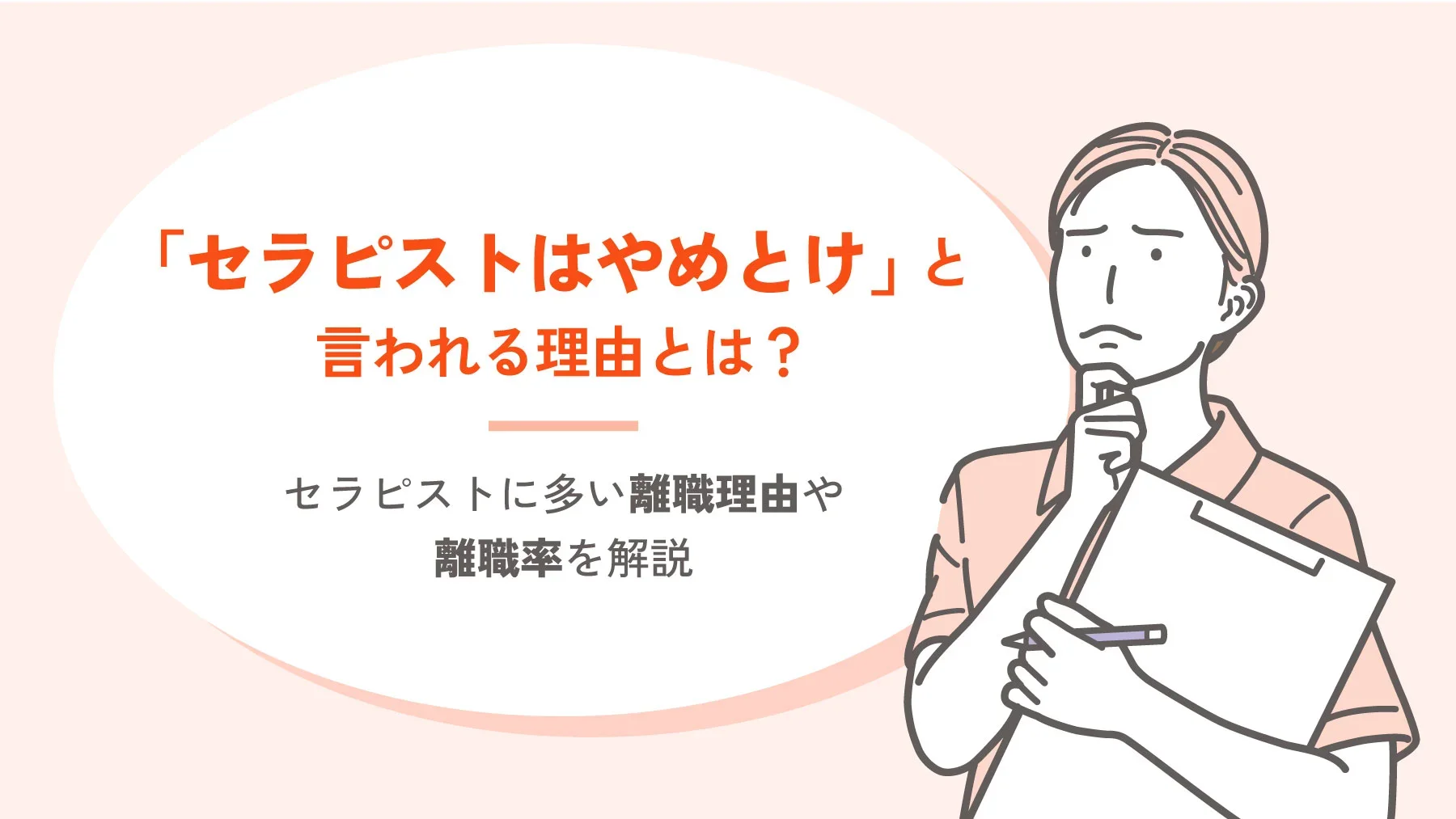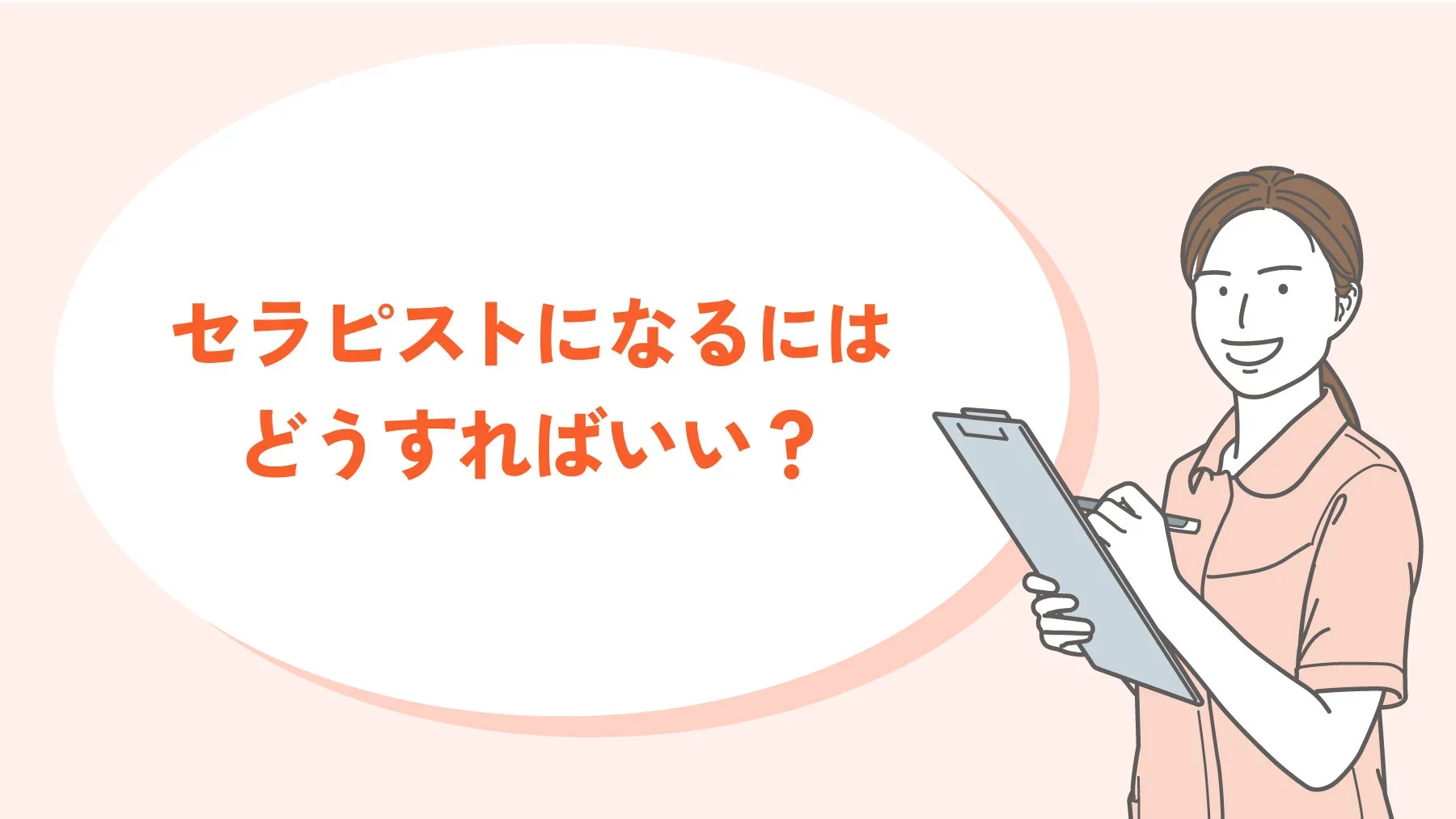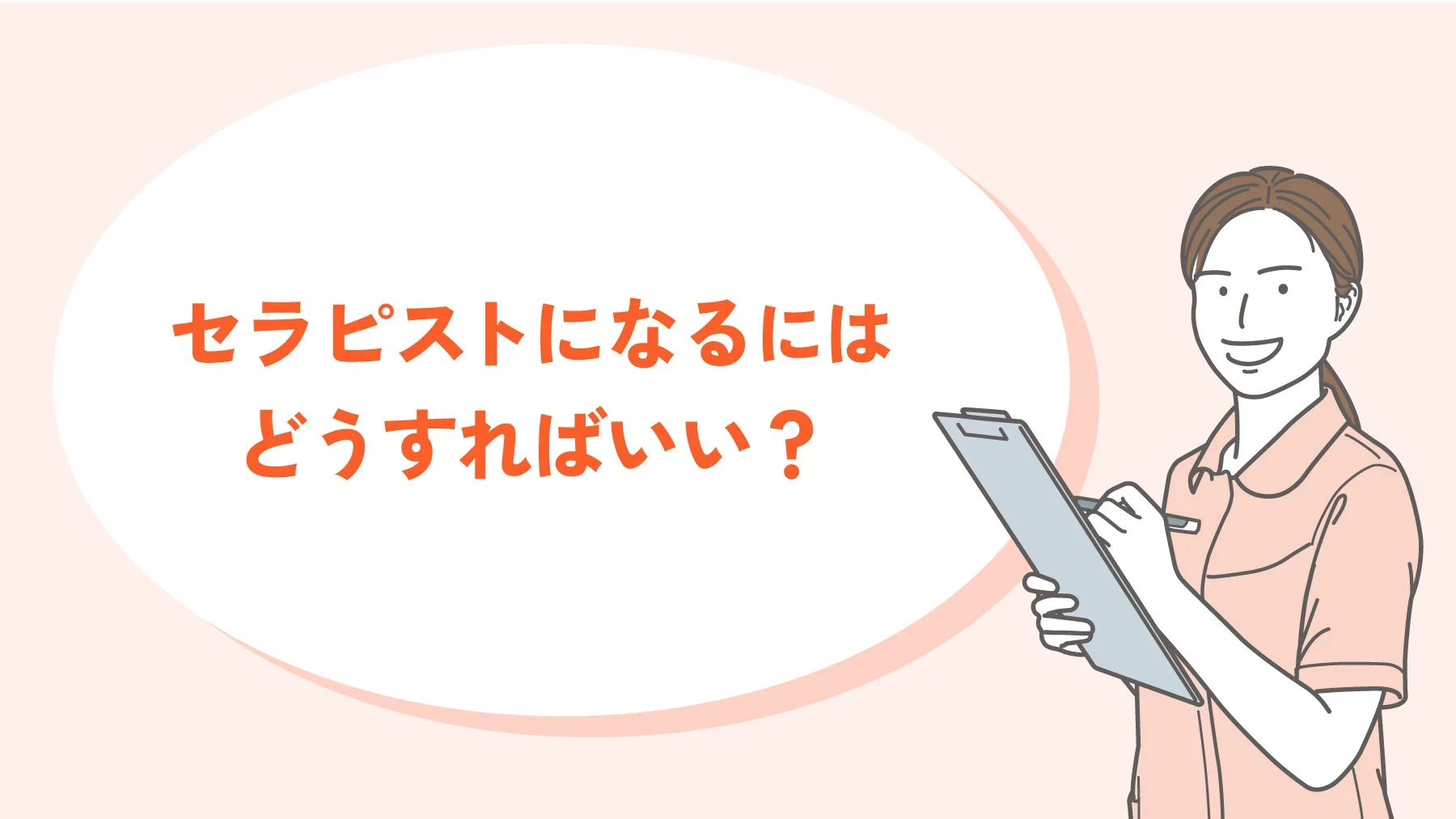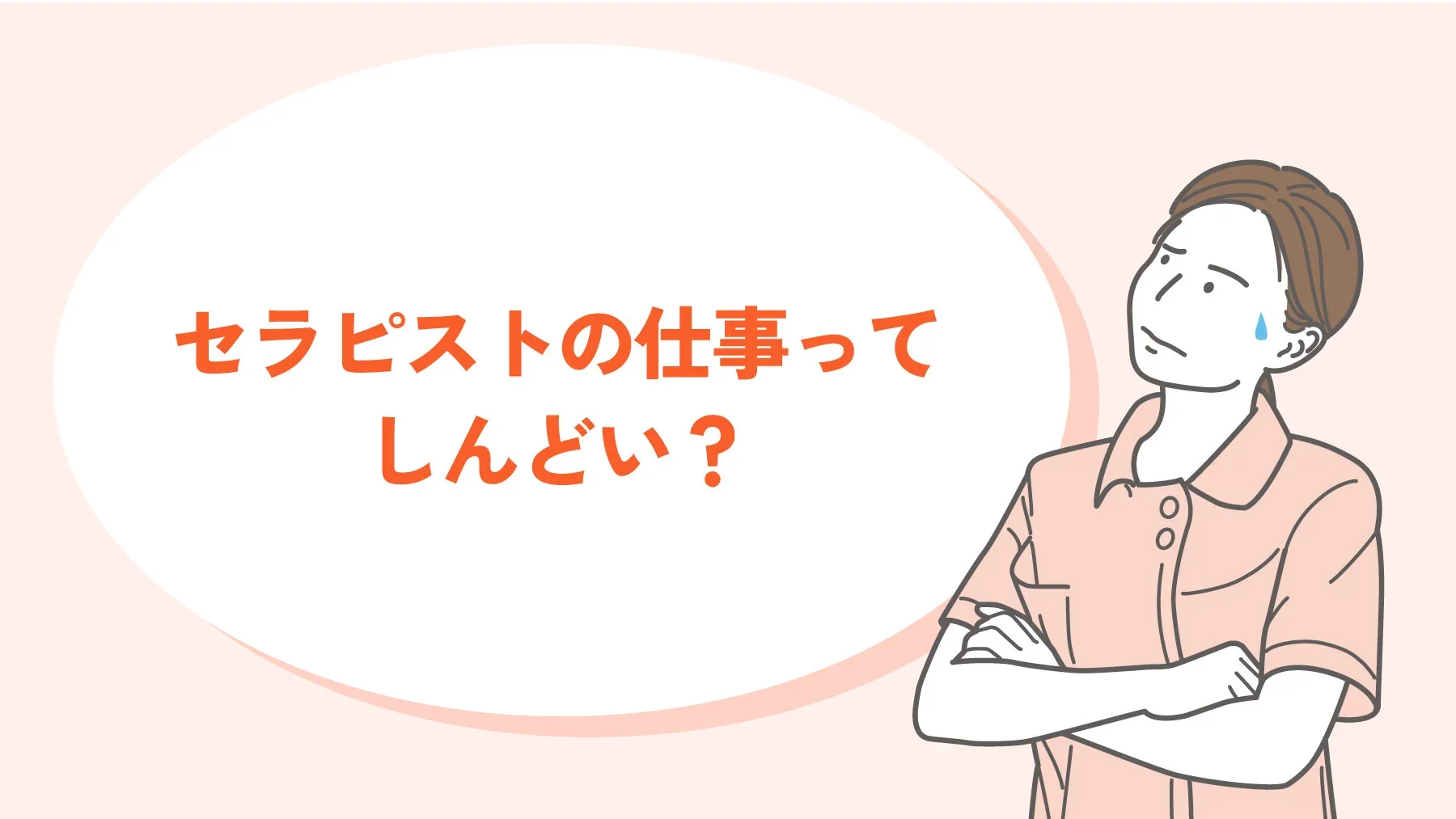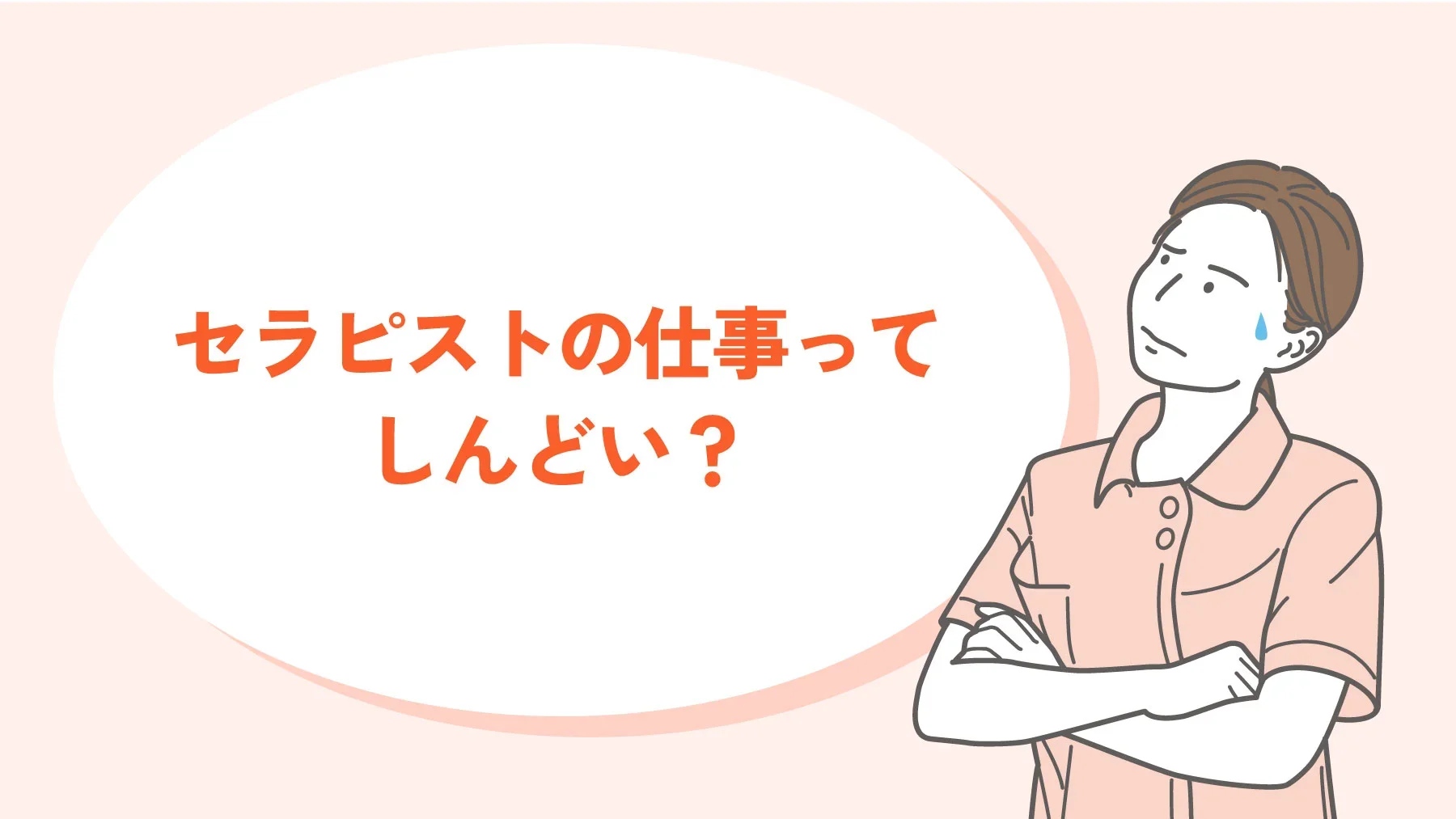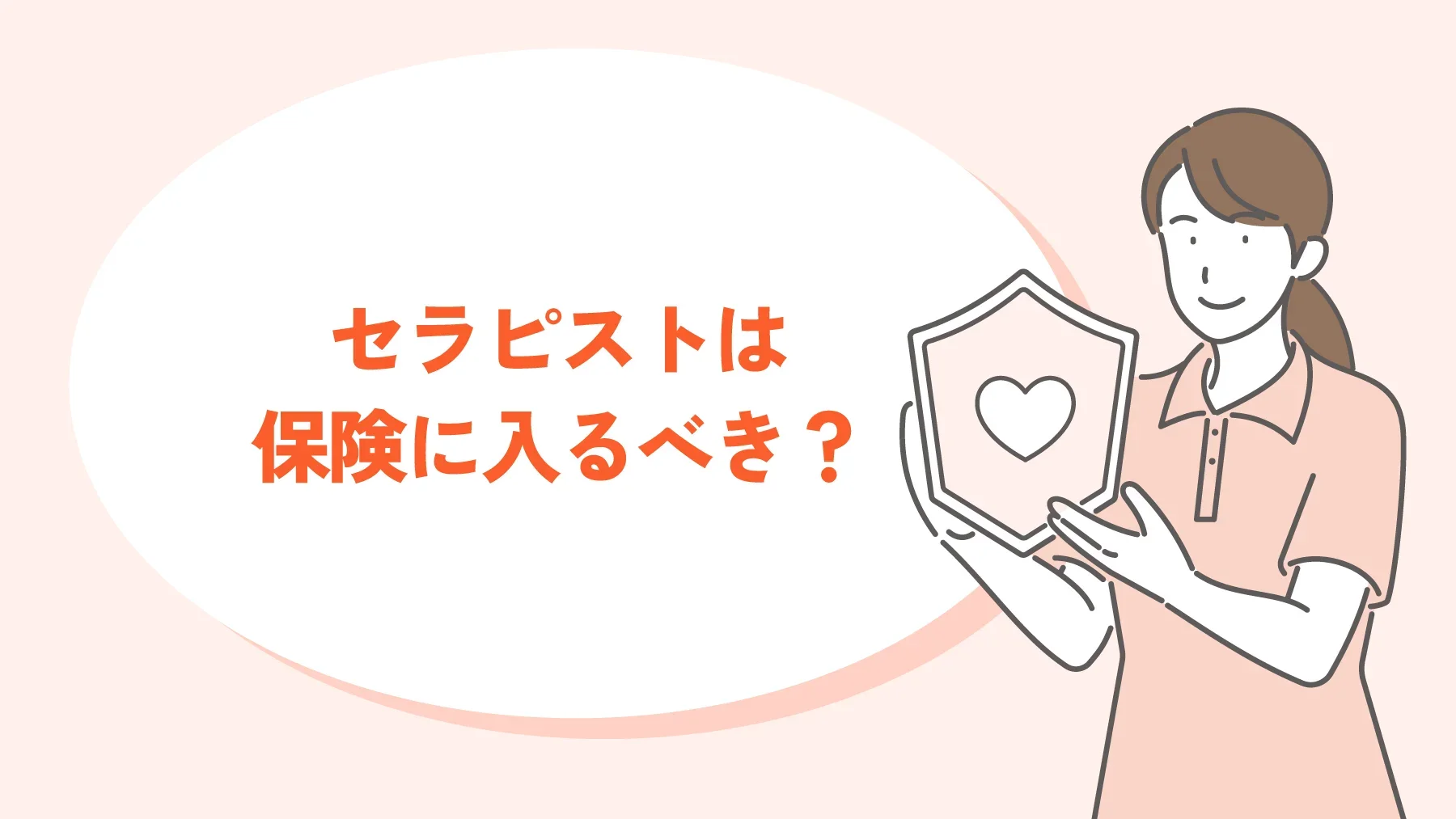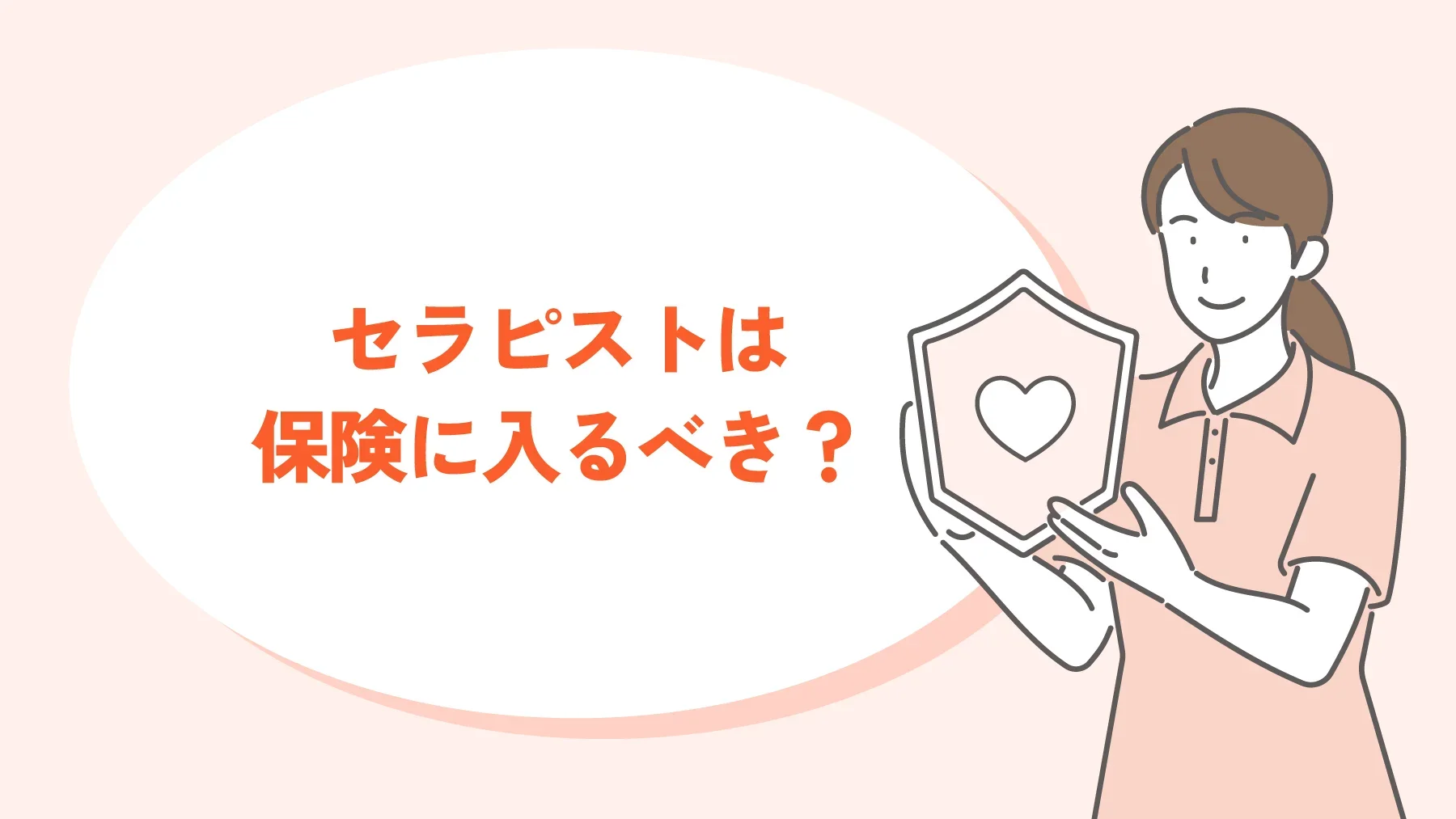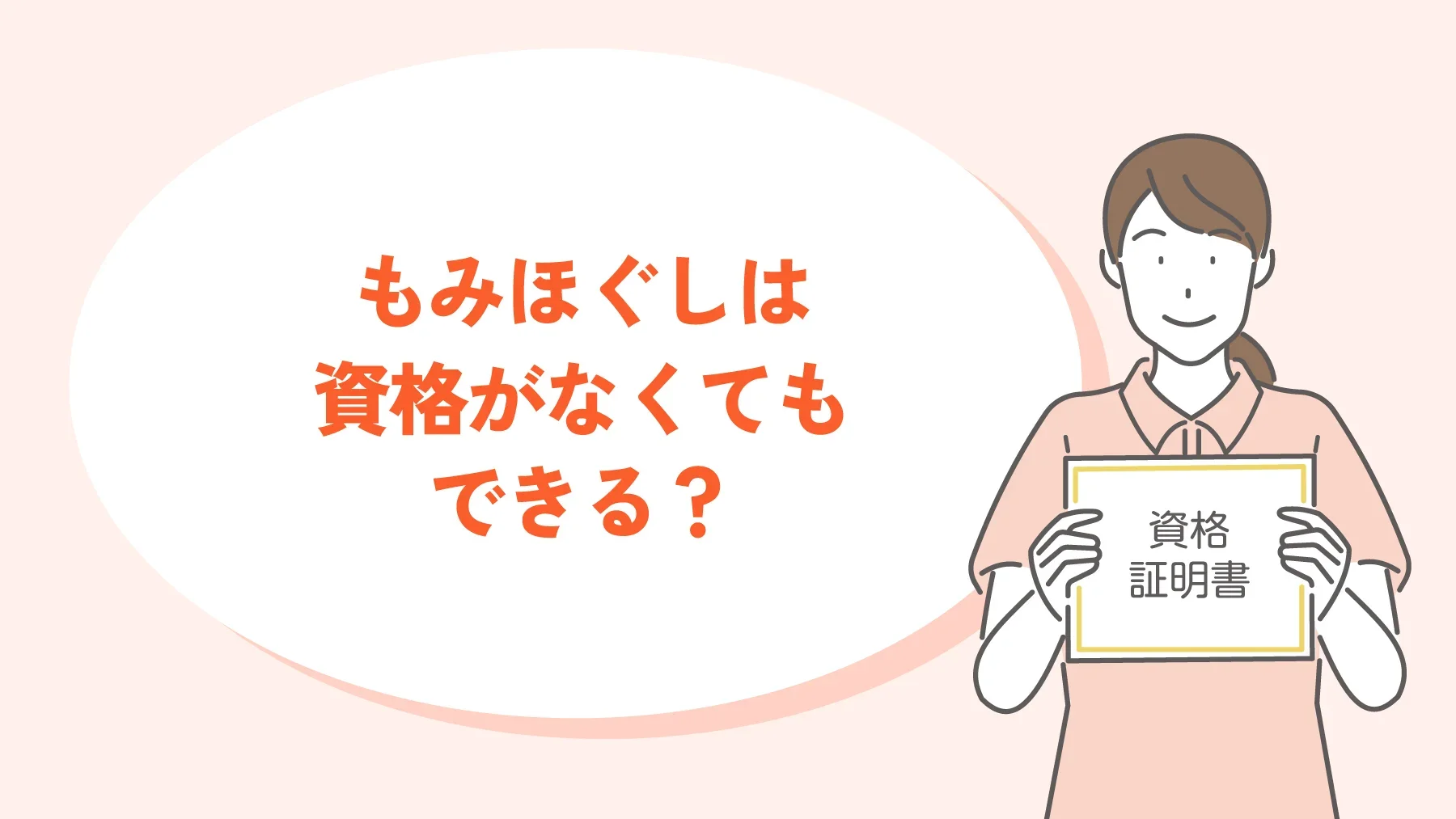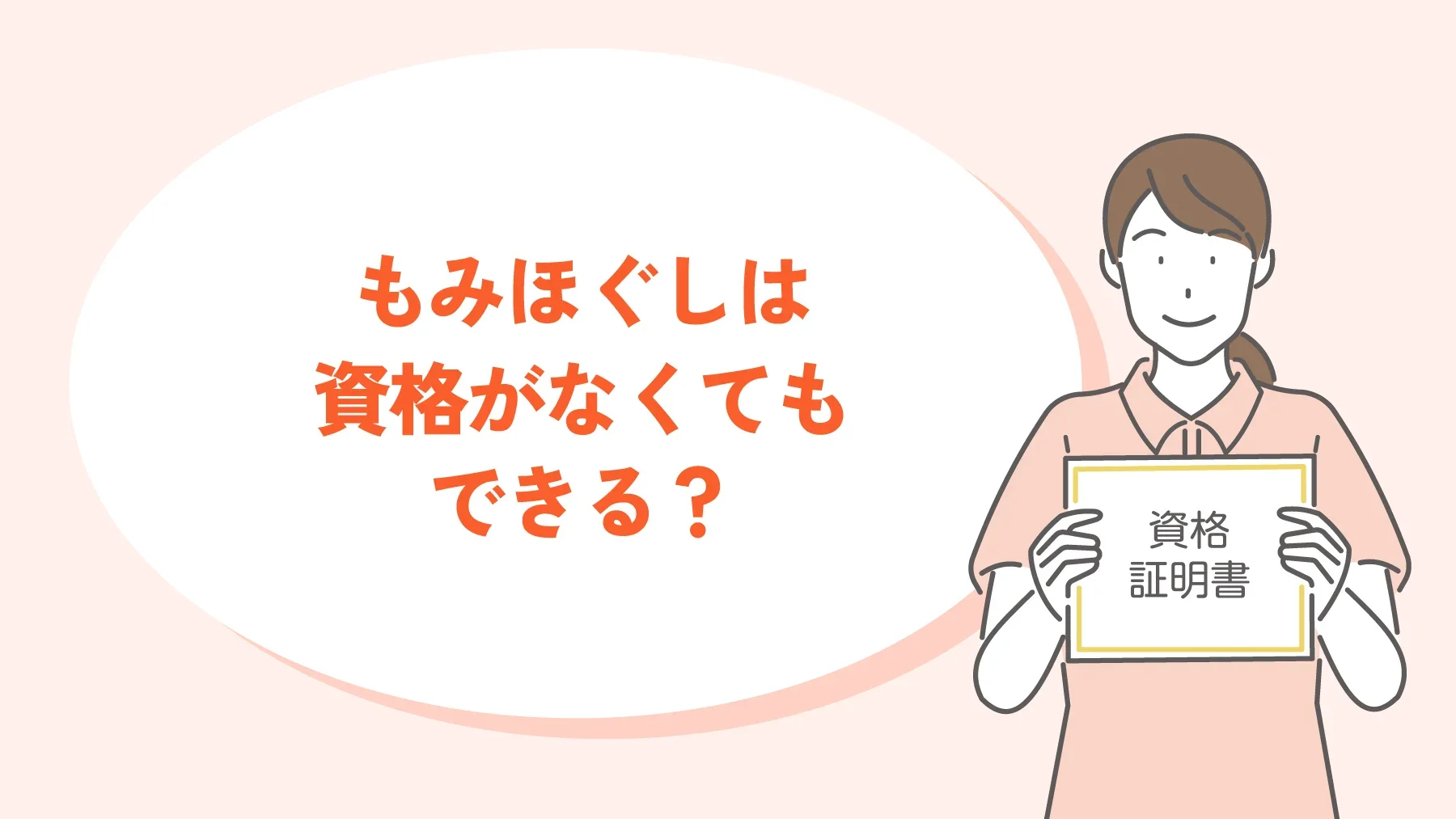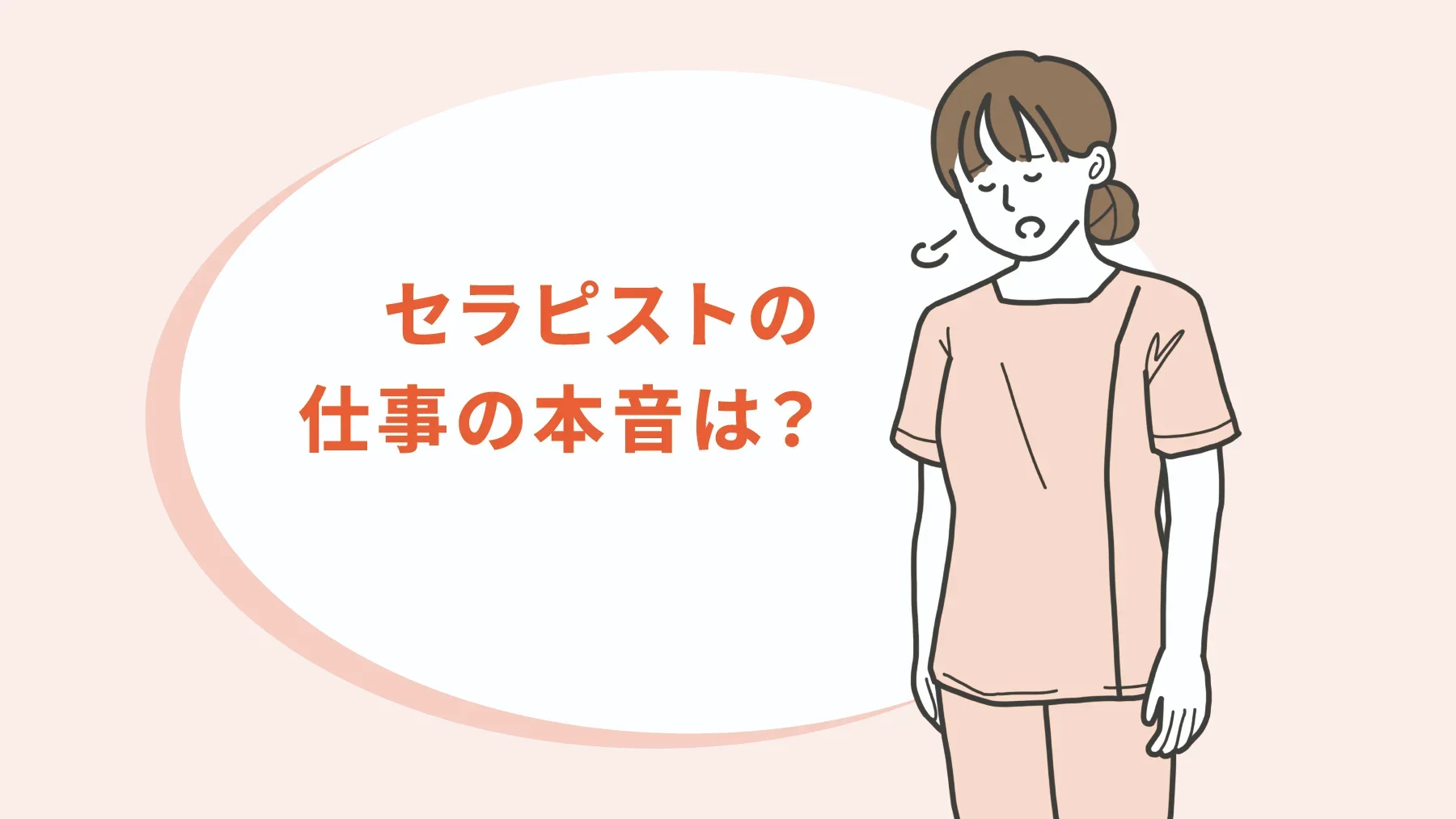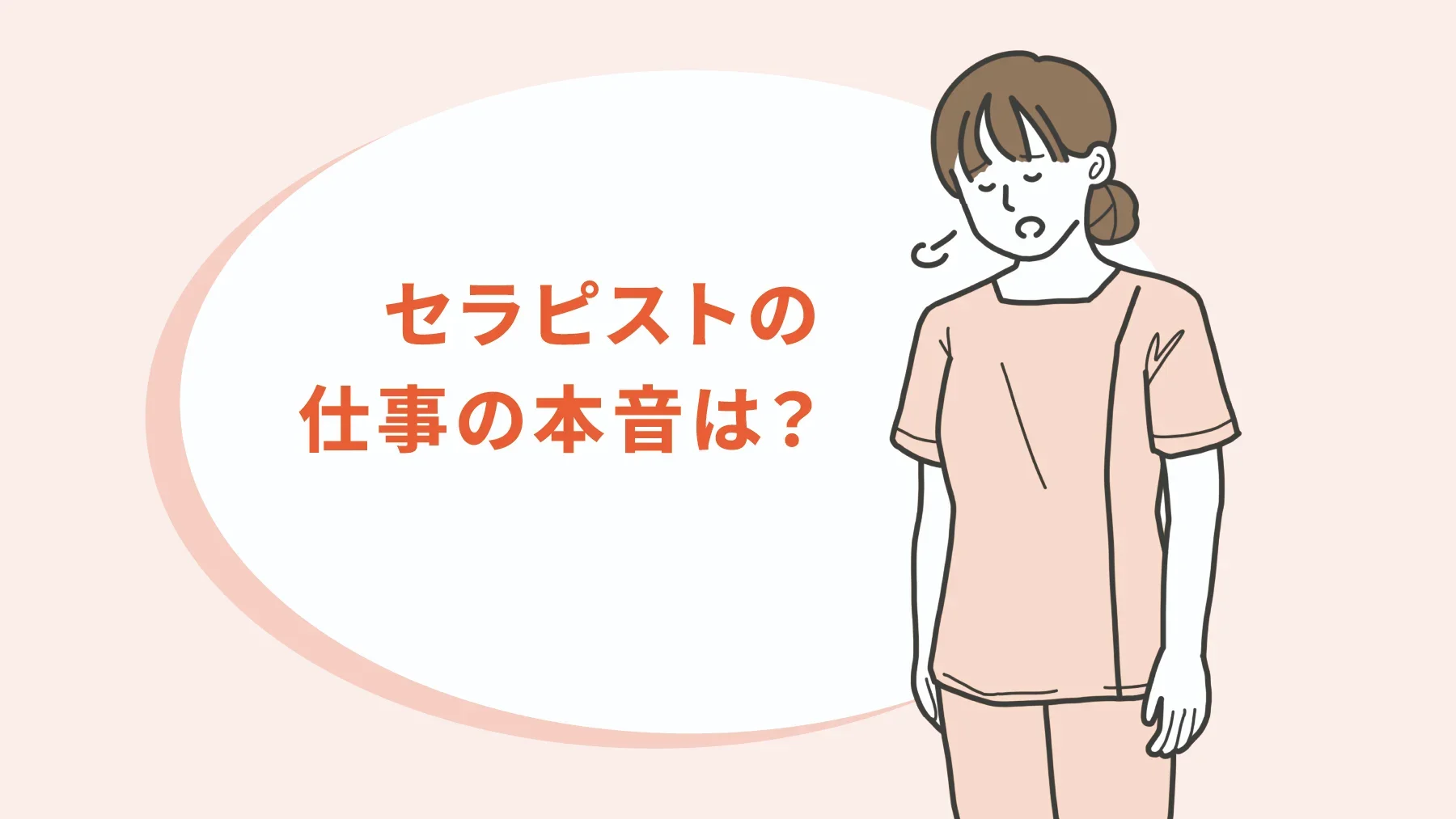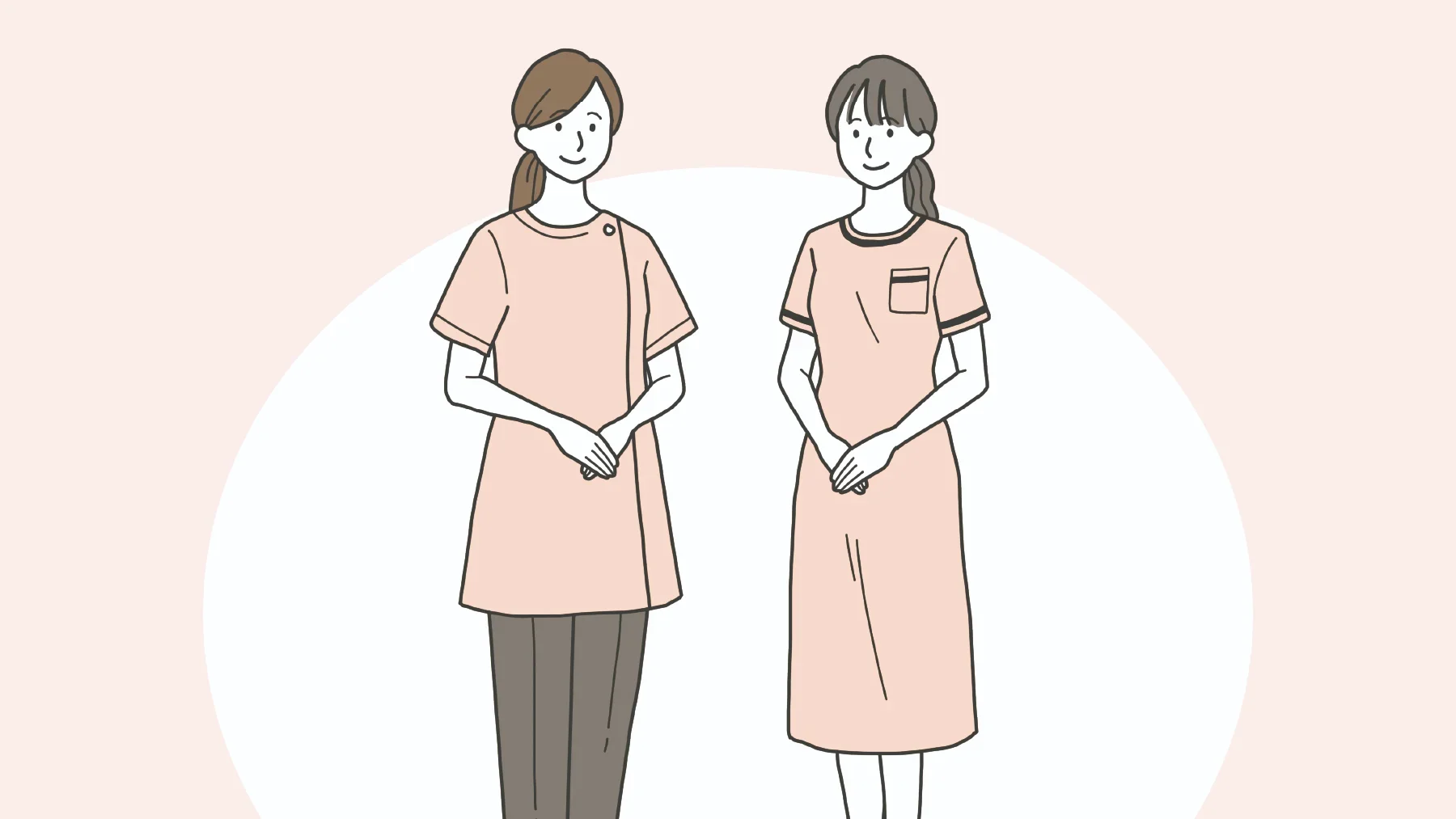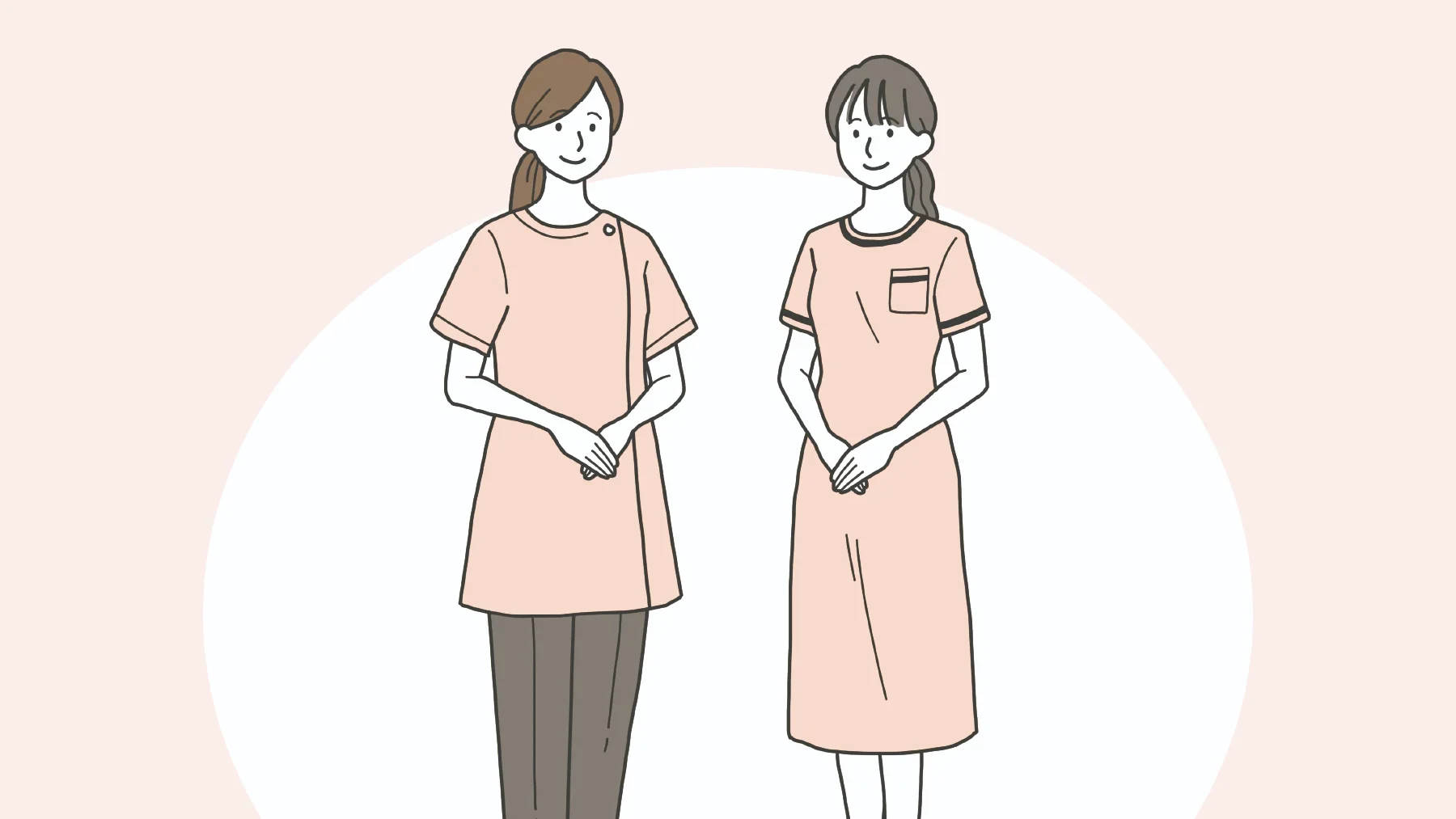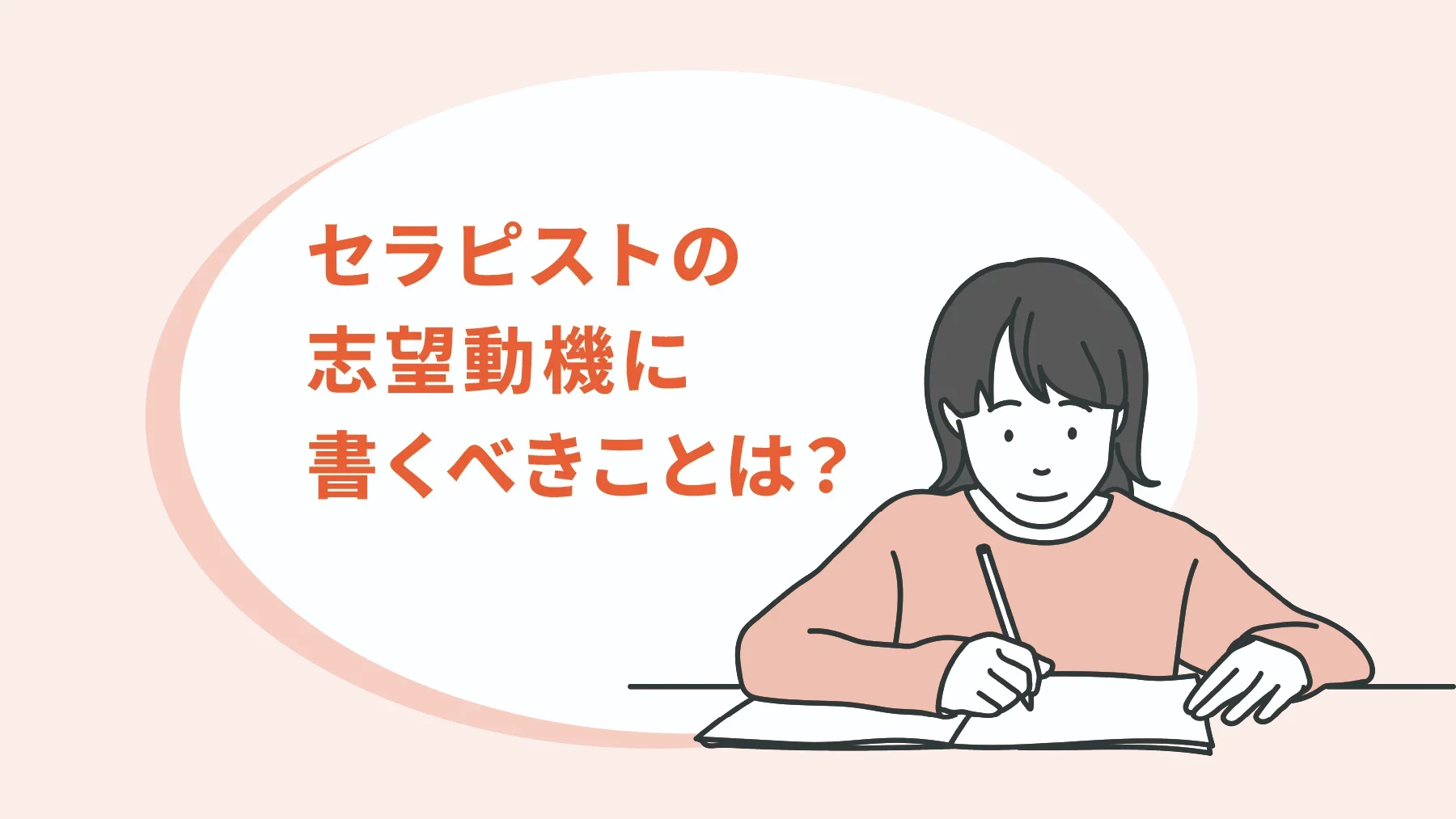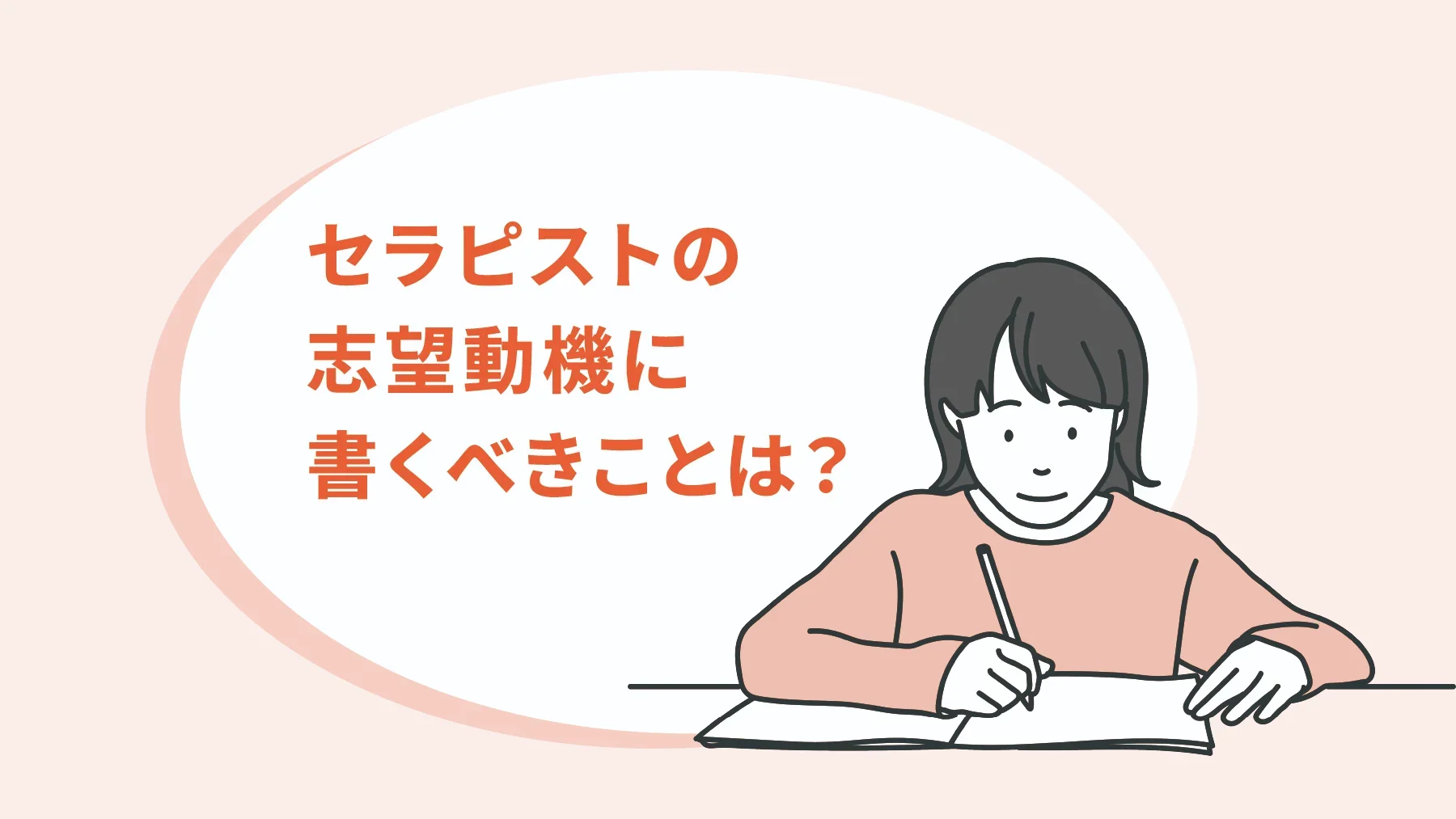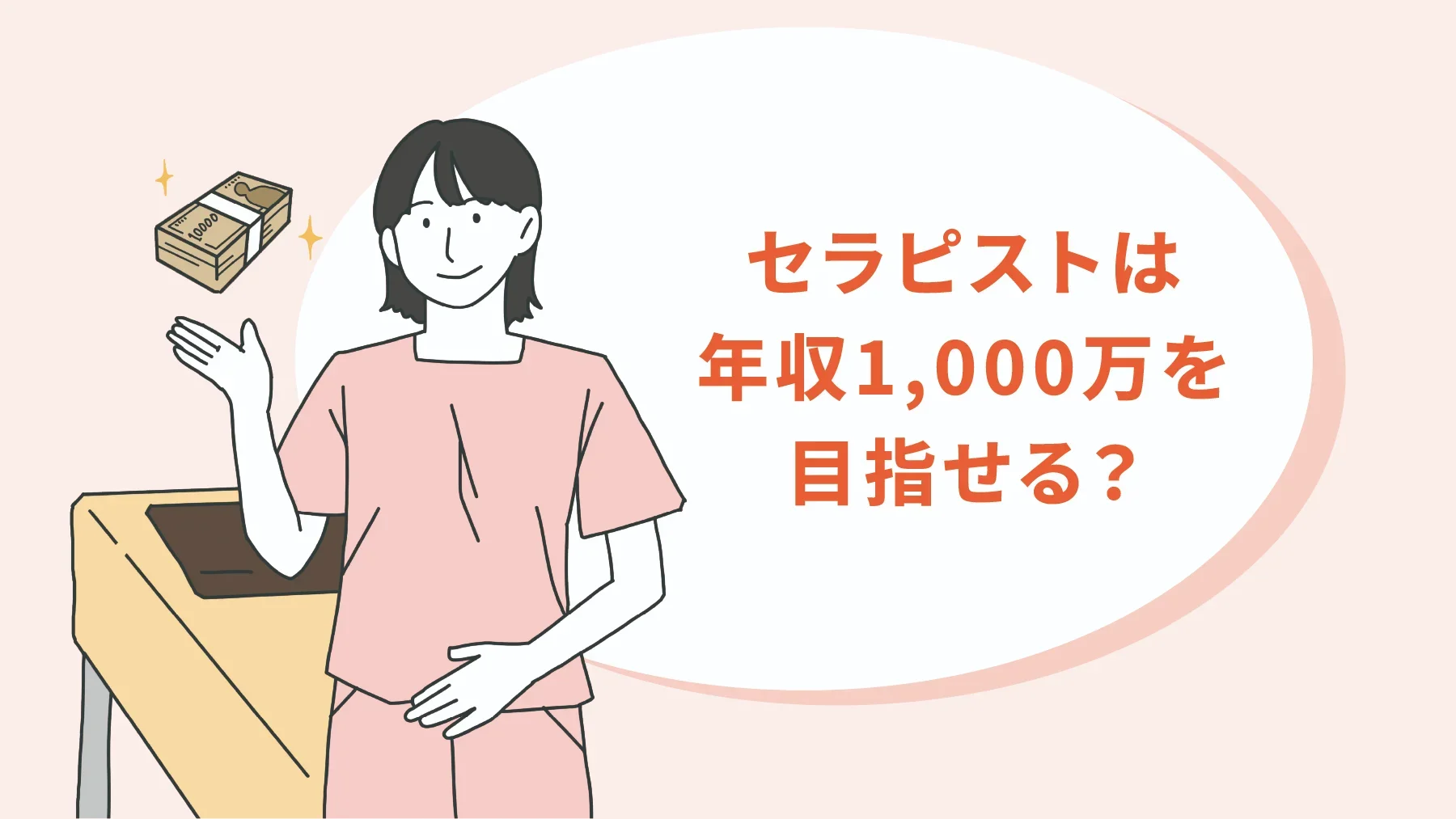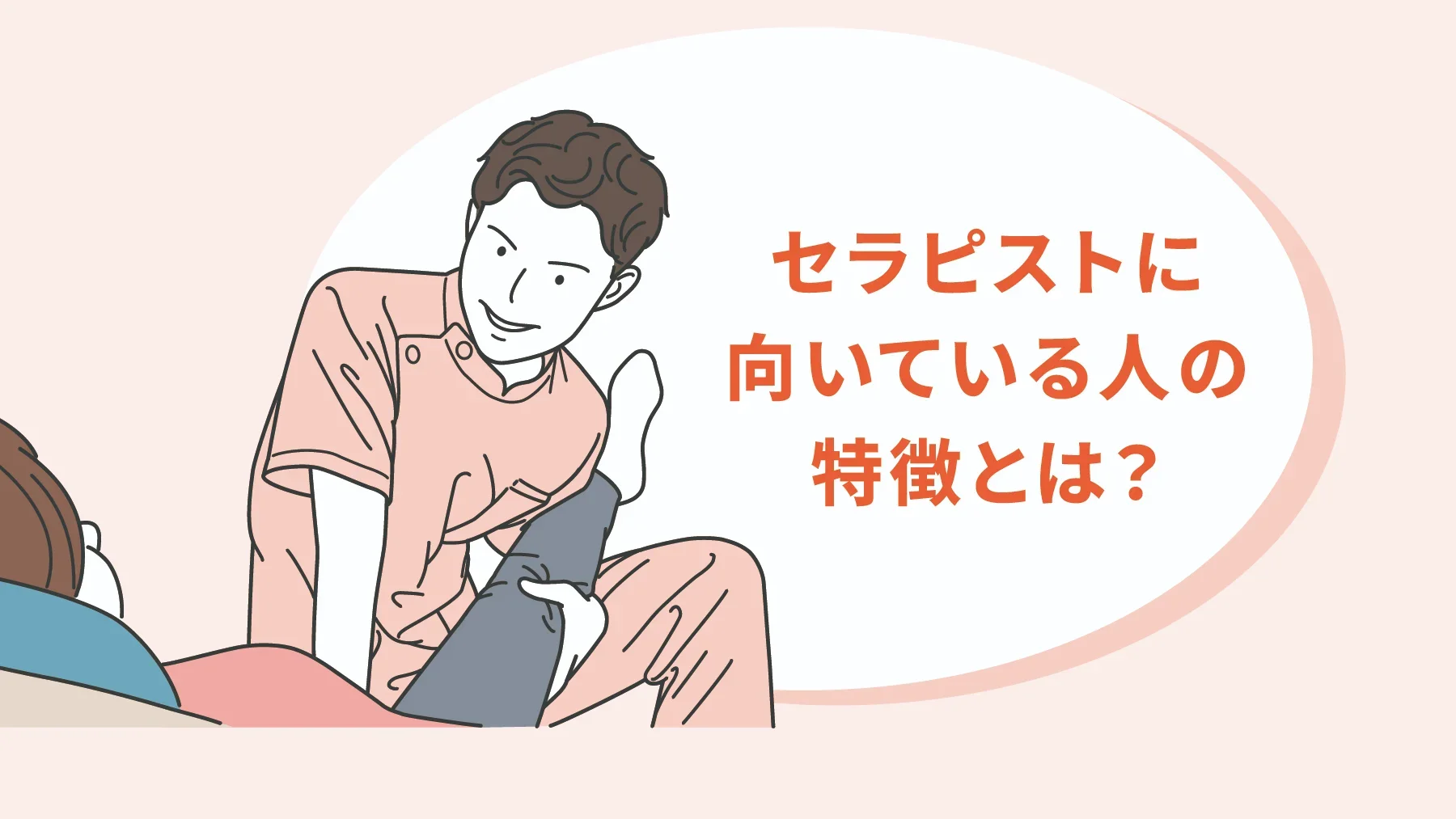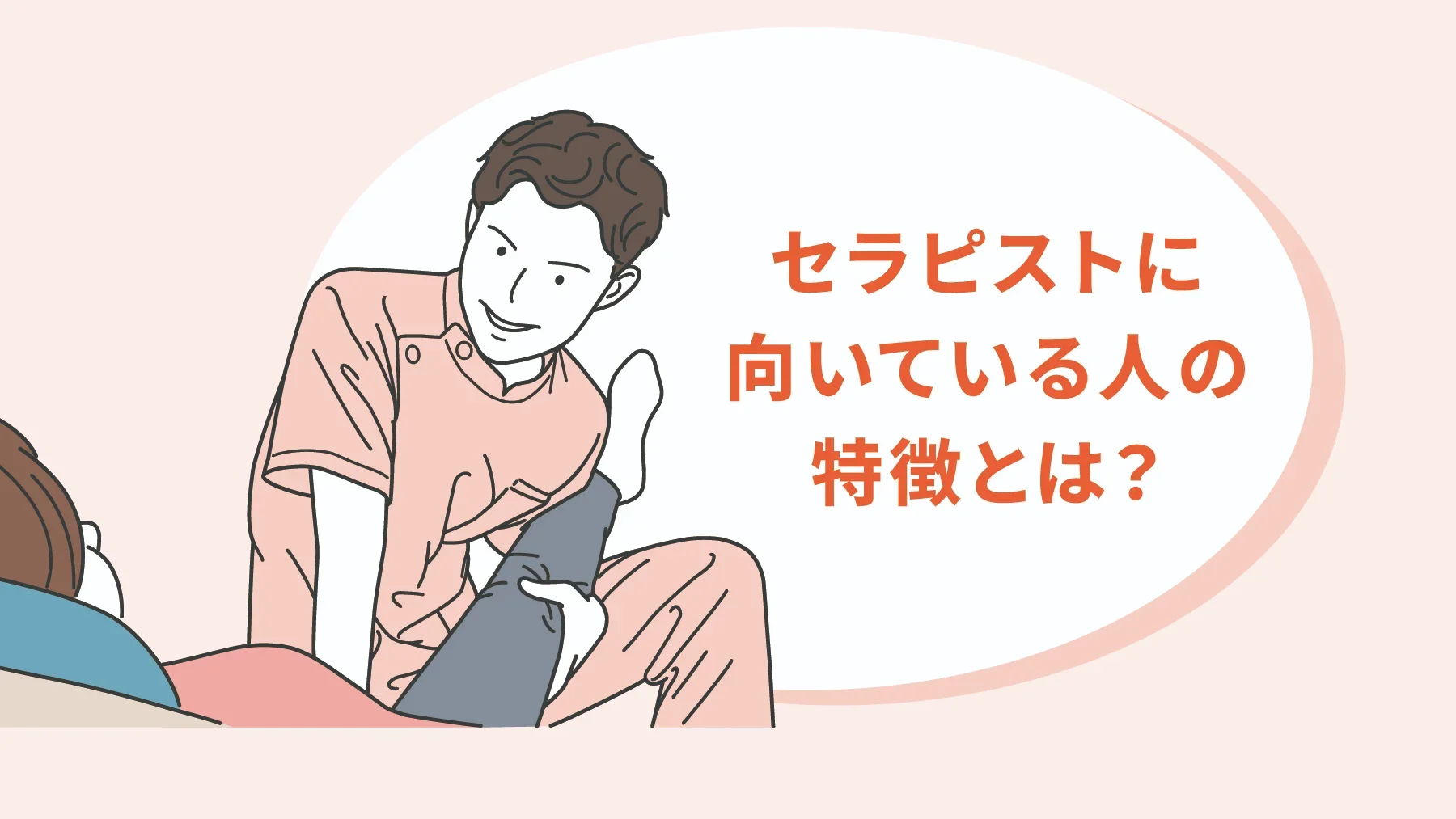-
-
心身の疲れを癒し、リラクゼーションや美容を提供する「セラピスト」の働き方には、正社員として業務を行う方法のほか、業務委託の形態もあります。「自由に働きたい」「スキルを活かして高収入を目指したい」といった理由から、業務委託としての働き方に関心を持つ方も増えています。
しかし、実際に目指すとなると、「正社員との違いは?」「自分に本当に合った働き方なのだろうか」と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、セラピストが業務委託で働く場合のメリット・デメリット、働く場所を選ぶポイントについて解説します。
| 【この記事で分かること】 ・セラピストが業務委託で働くメリット ・セラピストが業務委託で働くデメリット ・セラピストが業務委託で働く場所の選び方 |
セラピストの業務委託とは?
セラピストの業務委託とは、個人事業主としてサロンと契約し、施術ごとの歩合制で報酬を受け取る働き方です。
正社員やアルバイトとは異なり、雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶため、業務日や業務時間は基本的に自分で決めることができ、働いた分だけ収入を得られます。
業務先は契約したサロンとなり、確定申告や保険手続きなどは自分で行う必要があります。
自由度の高い働き方ができる一方で、福利厚生や収入の安定性には不安な点があるため、自分に合った働き方かどうかをよく検討することが大切です。
セラピストが業務委託で働くメリット
働き方が多様化する現代において、業務委託はフリーランスとして活動するセラピストにとって魅力的な選択肢の一つです。業務委託で働くメリットを活かすことで、より効果的なキャリア構築につながります。
セラピストが業務委託で働くメリットは、大きく以下の4つです。
- 歩合制度や指名制度により高収入を目指せる
- 仕事に必要な支出は経費に計上できる
- ライフスタイルに合わせた働き方ができる
- 施術に集中しやすい環境で働ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
歩合制度や指名制度により高収入を目指せる
業務委託で働くセラピストの多くは、施術件数や指名数に応じて報酬が決まる「歩合制」を採用しています。自分の努力が報酬に反映されるため、高いモチベーションを保ちやすく、結果次第で高収入を目指せることが魅力です。
また、サロンによっては指名料の全額を還元してもらえる場合もあり、さらに資格を取得することで資格手当を受け取れることもあります。これにより、自分のスキルを磨くほど収入アップにつなげられる点が大きなメリットです。
仕事に必要な支出は経費に計上できる
業務委託のセラピストは個人事業主として活動するため、事業に関連するさまざまな支出を経費として計上し、税金の控除を受けることが可能です。経費を計上することで課税対象となる所得を抑えられ、所得税や住民税の節税につながります。
セラピストの場合、具体的に以下のような費用が経費として認められます。
- レンタルサロンの利用料
- 事業で使用する範囲の店舗家賃
- ホームページの作成・維持費
- 広告費
- チラシや名刺の印刷費
- 研修やセミナーの参加費
- 専門書籍の購入費
- 施術で使うオイルや精油の購入費
- 仕事で利用した交通費
- イベントへの出店料 など
ただし、事業と直接関係のないプライベートな生活費や所得税・住民税、医療費や保険料などは経費に含めることはできません。経費計上によって賢く収入を管理し、税負担を抑えることが重要です。
ライフスタイルに合わせた働き方ができる
業務委託のセラピストは、働く時間や休日を自分の裁量で決められるため、自由度の高さが魅力です。
サロンとの事前の取り決めは必要ですが、個人のスケジュールに合わせて柔軟に働くことが可能なため、育児や介護といったプライベートの状況と両立しやすいでしょう。
自身のライフスタイルやライフステージに合わせ、無理なくキャリアを継続できる点は、業務委託ならではのメリットといえます。
施術に集中しやすい環境で働ける
業務委託のセラピストの場合、雇用契約とは異なり、契約範囲外の雑務を依頼されることは基本的にはありません。そのため、セラピストとしての専門業務である「お客様への施術」に集中でき、サービスの質向上にもつながります。
施術以外の業務に追われることがないため、精神的な負担が少なく、より良いコンディションで仕事に臨めることがメリットです。
セラピストが業務委託で働くデメリット
セラピストの業務委託という働き方には多くのメリットがある一方で、事前に知っておくべきデメリットもあります。これらを知らずに働き始めると、独立後に働き方や収入面でミスマッチが生じる可能性があるため、注意が必要です。
セラピストが業務委託で働く上で考えられる主なデメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 福利厚生を受けられない
- 収入が安定しにくい
- 自分で確定申告を行う必要がある
それぞれ詳しく見ていきましょう。
福利厚生を受けられない
業務委託として働くセラピストは個人事業主となるため、サロンが提供する社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険には加入することはできません。
また、国民健康保険や国民年金への加入手続きは、すべて自分自身で行う必要があります。
正社員などに支給される賞与(ボーナス)や退職金、住宅手当といった福利厚生も対象外です。
病気や怪我で休業した際の傷病手当金のような保障もないため、民間保険に加入するなど、自身でリスクに備えることが大切です。
収入が安定しにくい
業務委託は固定給のない完全歩合制であるため、来客数や施術件数によって収入が変動し、安定しにくい点がデメリットです。
来客数が季節や天候に影響されたり、体調不良で休んだ場合にはその分の収入がゼロになる可能性もあります。
また、収入の不安定さから、クレジットカードやローンの審査で不利になるなど、社会的信用を得にくい場合もあるでしょう。
そのため、計画的な貯金や複数の収入源を確保するなど、収入の波に備えた対策が不可欠です。
自分で確定申告を行う必要がある
業務委託は個人事業主の扱いとなるため、会社による年末調整はなく、毎年自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告の手続きは専門知識が求められ、特に複数の場所で働いている場合は収支の管理が複雑になりやすいです。
税務に関する基本的な知識を身につけ、日頃から帳簿付けを習慣化するなど、計画的な対応が必要になります。
セラピストが業務委託で働く場所の選び方
業務委託で働く場所の探し方には、求人サイトで「業務委託」の条件で探すほか、働きたいサロンの公式サイトをチェックしたり、直接問い合わせたりする方法があります。
ミスマッチを防ぎ、長く安心して働くためには、応募前に以下の点をチェックしておくと良いでしょう。
- 施術スタイル:自分の得意分野や希望する施術内容と合っているか
- 立地と客層:通いやすさやお客様の年齢層・ニーズを確認
- 料金設定:求められる技術や接客レベルの指標になる
- スタッフやお店の雰囲気:職場の人間関係や働きやすさを把握
- 研修制度の有無:スキルアップのサポート体制を確認
これらを意識することで、長く安心して働ける職場に出会える可能性が高まります。
リラクゼーションスペースの「りらくる」では、全国600店舗以上から働く場所を選ぶことが可能です。また、自分の都合にあわせて日程や時間を選び自由に働くことができます。
さらに、5万人の育成実績を持つトレーナー人による研修制度があり、働きながら専門知識を学べるため、未経験の方でも安心してスタートできます。
努力次第で収入を増やせる制度もあり、未経験でも60分あたり2,340円から働き始められます。
業務委託での働き方に興味がある方は、ぜひ一度「りらくる」にご相談ください。
セラピストの業務委託に関するよくある疑問
業務委託という働き方に興味はあるものの、「実際にはどのくらい稼げるの?」「手続きや保険はどうすればいいの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、業務委託を始める方からよく寄せられる質問に、わかりやすくお答えします。
業務委託のセラピストは稼げる?
業務委託の場合、収入面が気になる方も多いかと思いますが、結論として、技術力を磨くことで収入を大きく伸ばすことが可能です。
業務委託の報酬は基本的に完全歩合制で、施術件数や指名数が多いほど報酬は増加していきます。自分の努力がそのまま収入に反映されるため、 やりがいも感じやすいでしょう。
多くのサロンでは、基本の歩合給に加え、指名料の還元や資格手当などスキルに応じた上乗せ制度があります。
また、サロンによっては技術レベルの向上や、集客への貢献度に応じて歩合率が上がるシステムを導入している場合もあり、努力次第で収入をさらに増やせる環境が整っています。
セラピストが業務委託で働く場合開業届の提出は必要?
セラピストが業務委託で働く場合、原則として開業届の提出が必要です。
業務委託で働くセラピストは個人事業主にあたるため、事業を開始してから1カ月以内に、管轄の税務署へ「開業届」を提出するよう定められています。
提出しなくても罰則はありませんが、開業届を提出しなければ、節税メリットの大きい「青色申告」が利用できず、税務上のメリットを十分に活かせません。スムーズな事業運営のためにも、早めの提出が推奨されます。
業務委託のセラピストは保険に加入すべき?
セラピスト向けの賠償責任保険は任意加入となっており、加入が義務付けられている保険はありません。
しかし、施術中のトラブルが発生した場合、個人事業主であるセラピスト自身も責任を問われる可能性があるため、保険に加入しておくことで安心して働くことができます。
セラピストはお客様の身体に直接触れる仕事であるため、施術中に怪我をさせてしまったり、衛生管理が原因で炎症などを引き起こしてしまったりするリスクはゼロではありません。そのため、保険に加入しておくことが推奨されます。
なお、個人で直接契約できる保険は限られており、多くの場合は保険会社と提携したセラピスト団体を通じて加入するのが一般的です。
>セラピストは保険に入るべき?セラピスト向け保険の選び方を解説
まとめ
セラピストの業務委託は、業務時間の自由度や頑張り次第で収入を伸ばせるなど、自分のペースで施術に集中したい方や、高収入を目指したい方に適した働き方です。
一方で、固定給ではなく歩合制が多く、社会保険に加入できない点や、確定申告の必要性といったデメリットの側面もあることを理解しておく必要があります。
業務委託で働く場所を探す際は、契約内容や研修制度の有無、施術メニューや客層などを確認し、自分に合った職場を見極めることが大切です。
サポート体制の整った環境で安心して業務委託を始めたい方には、全国に600店舗以上を展開する「りらくる」でのお仕事がおすすめです。
未経験からでもプロのセラピストを目指せる研修制度が充実していますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。




 06-4400-5406
06-4400-5406