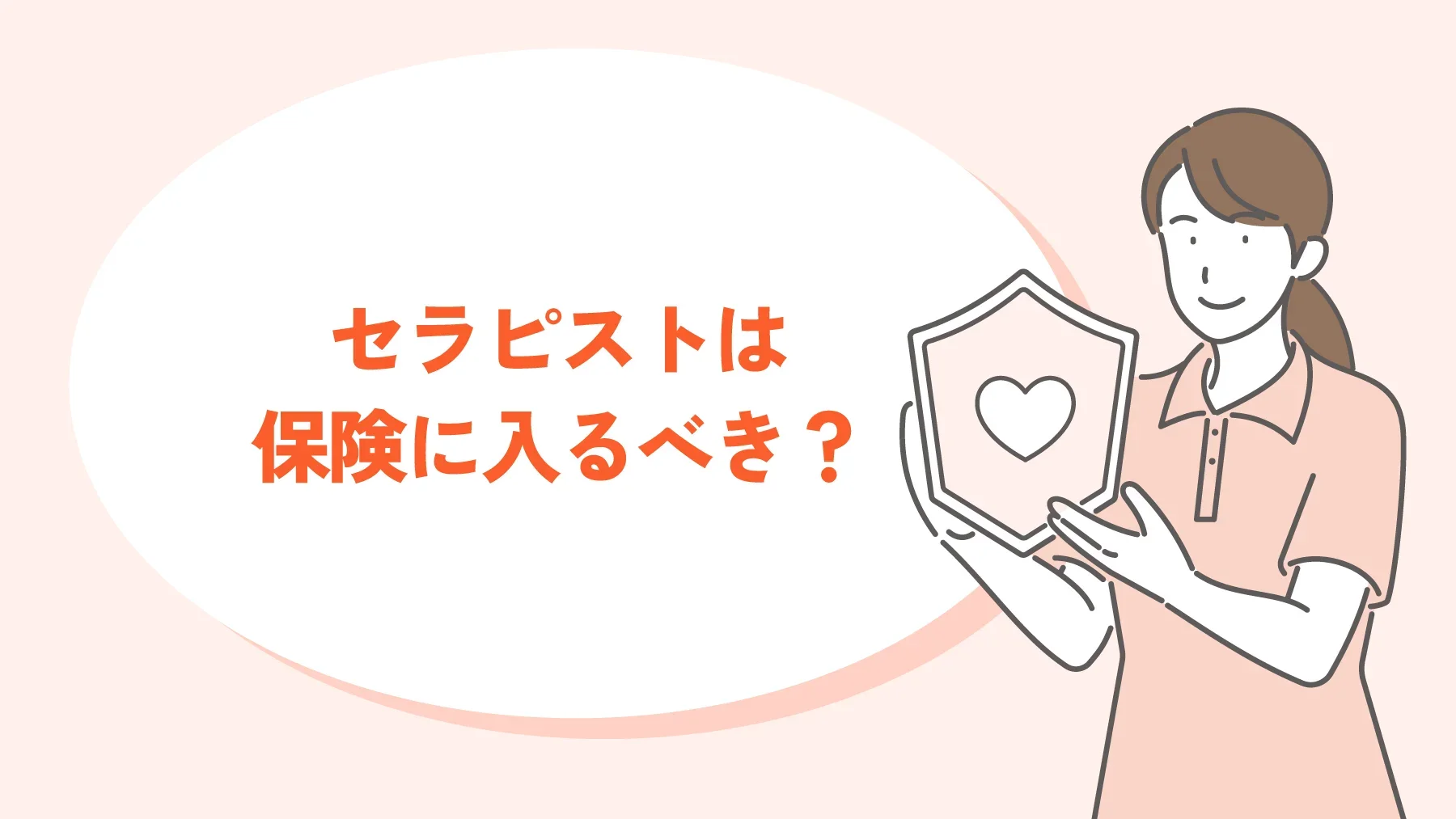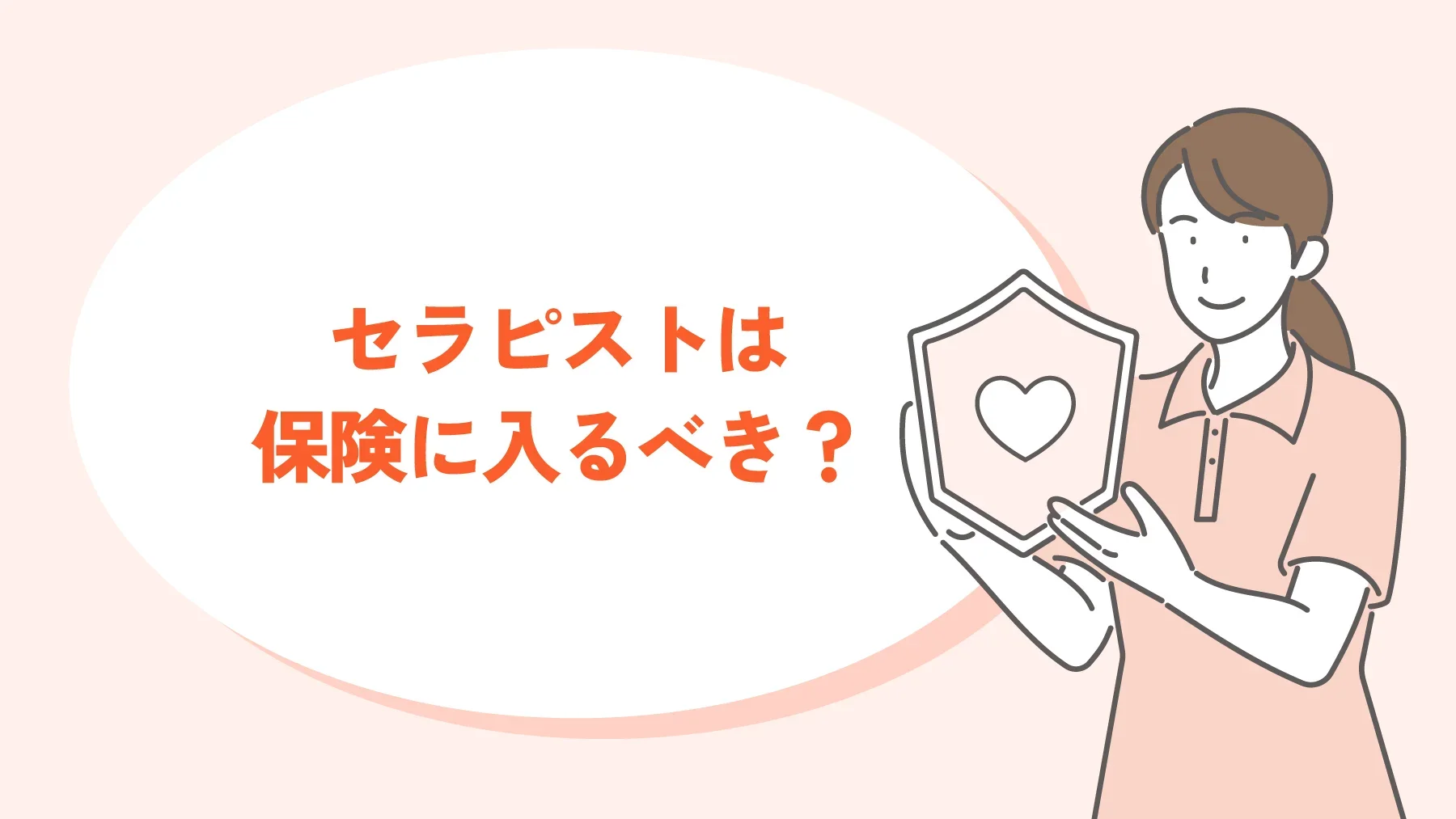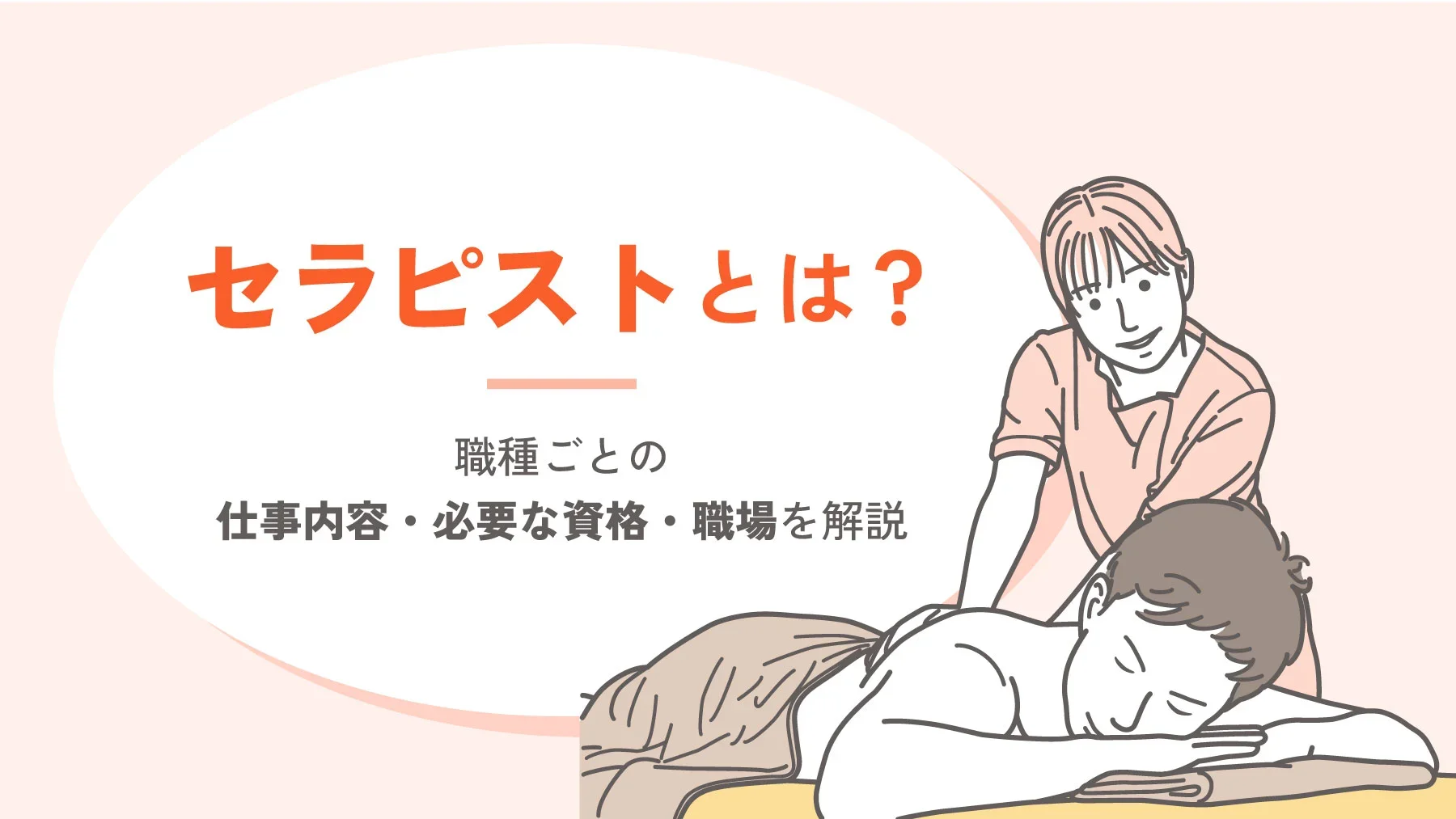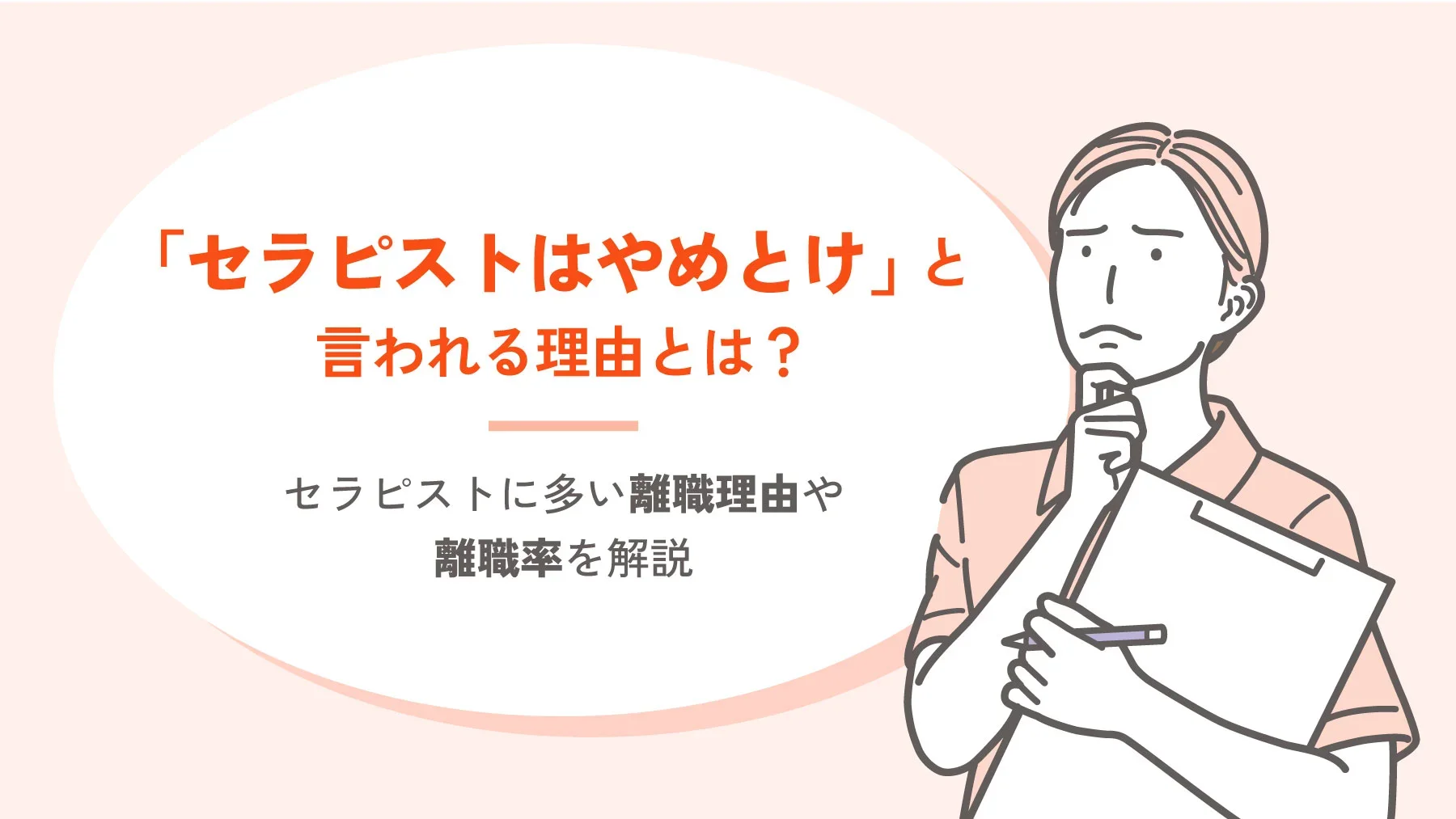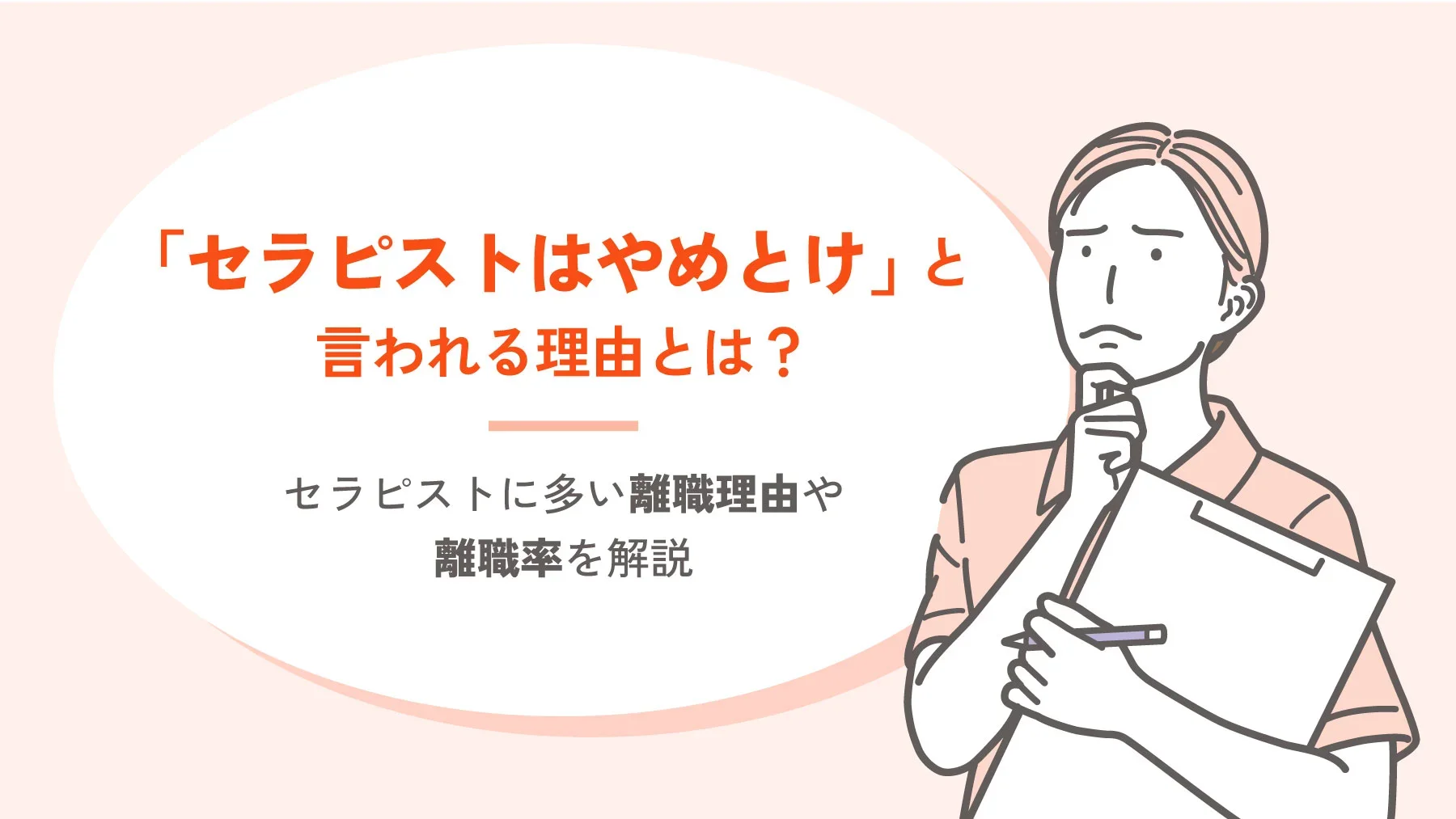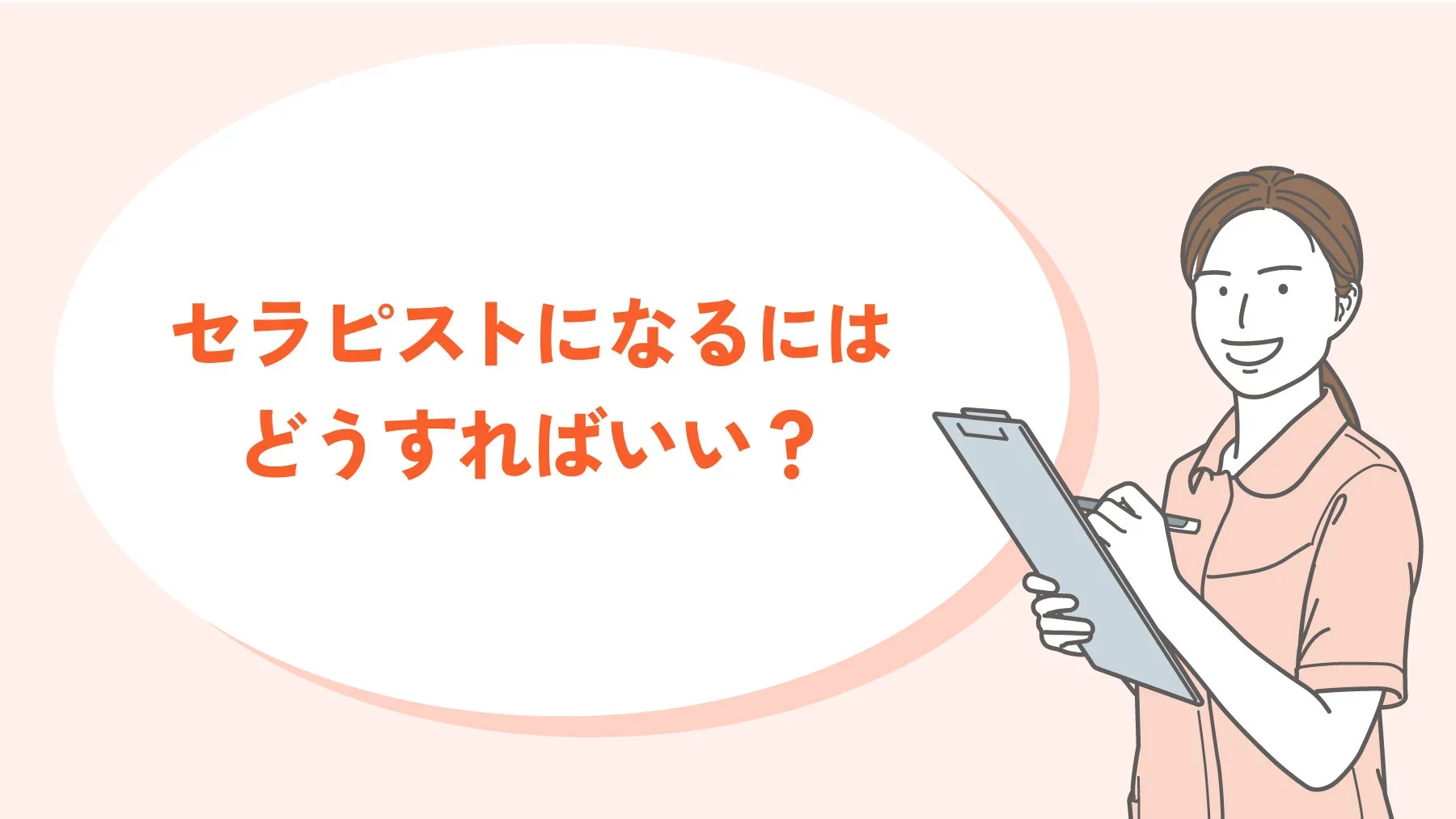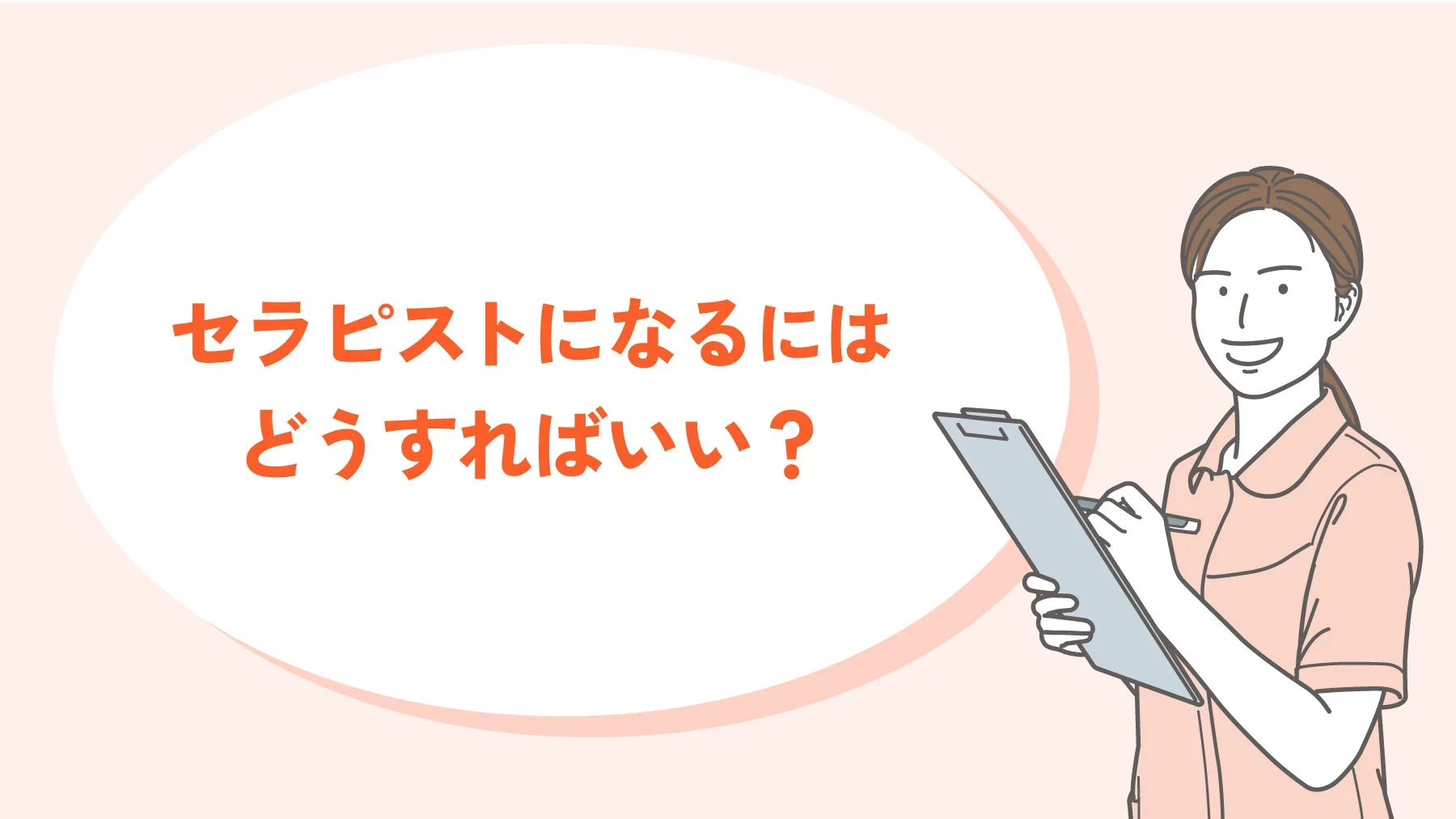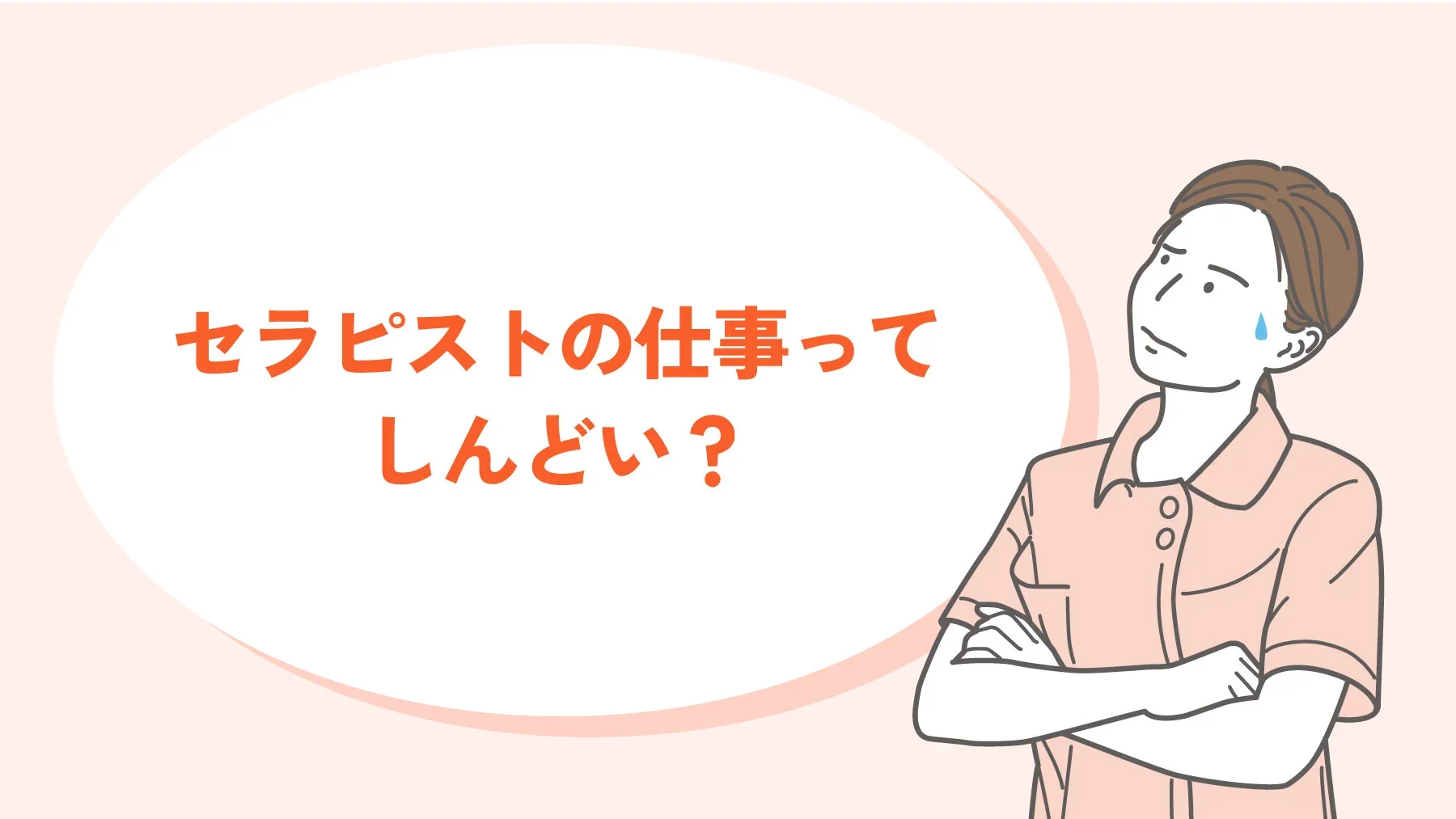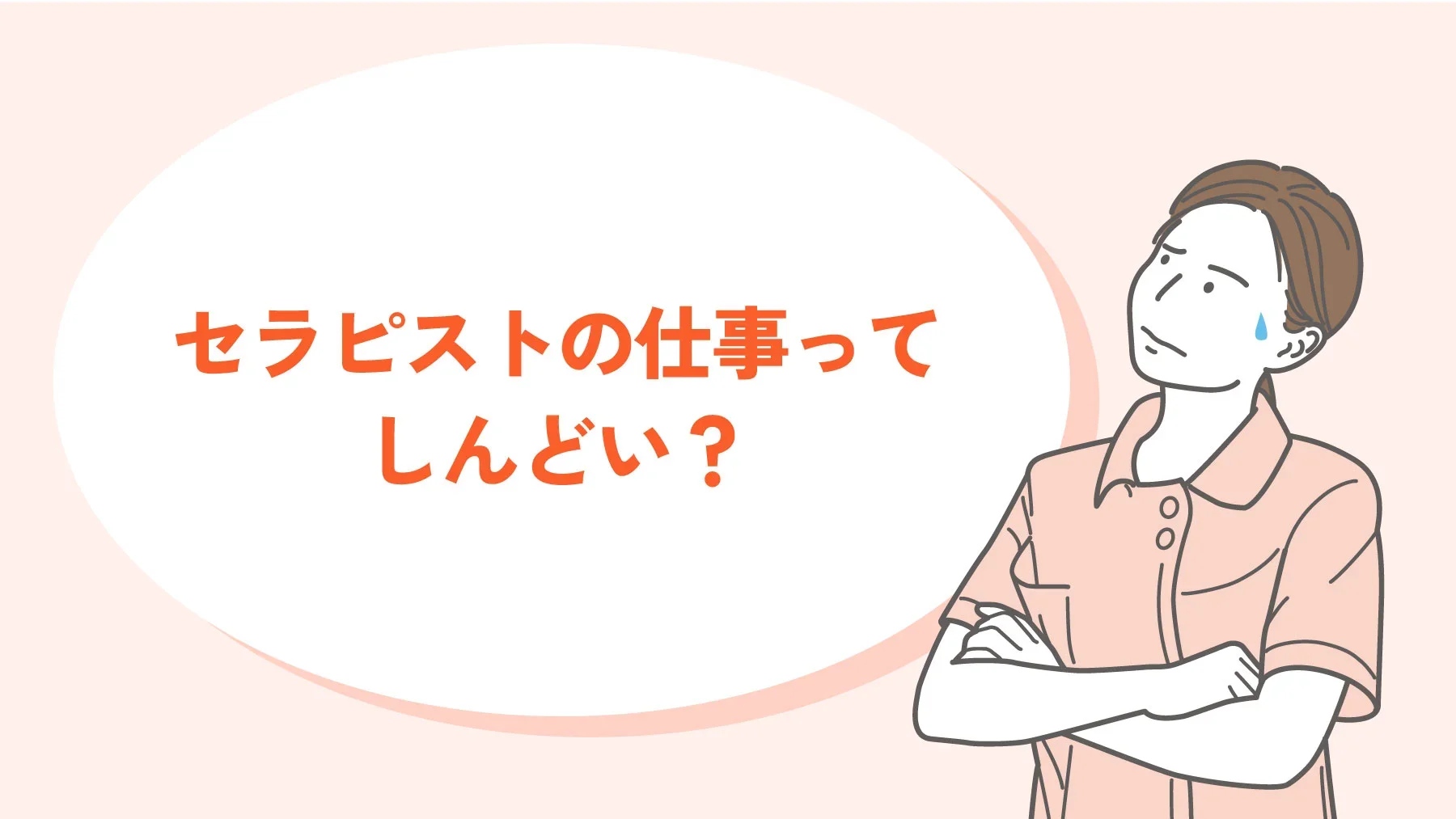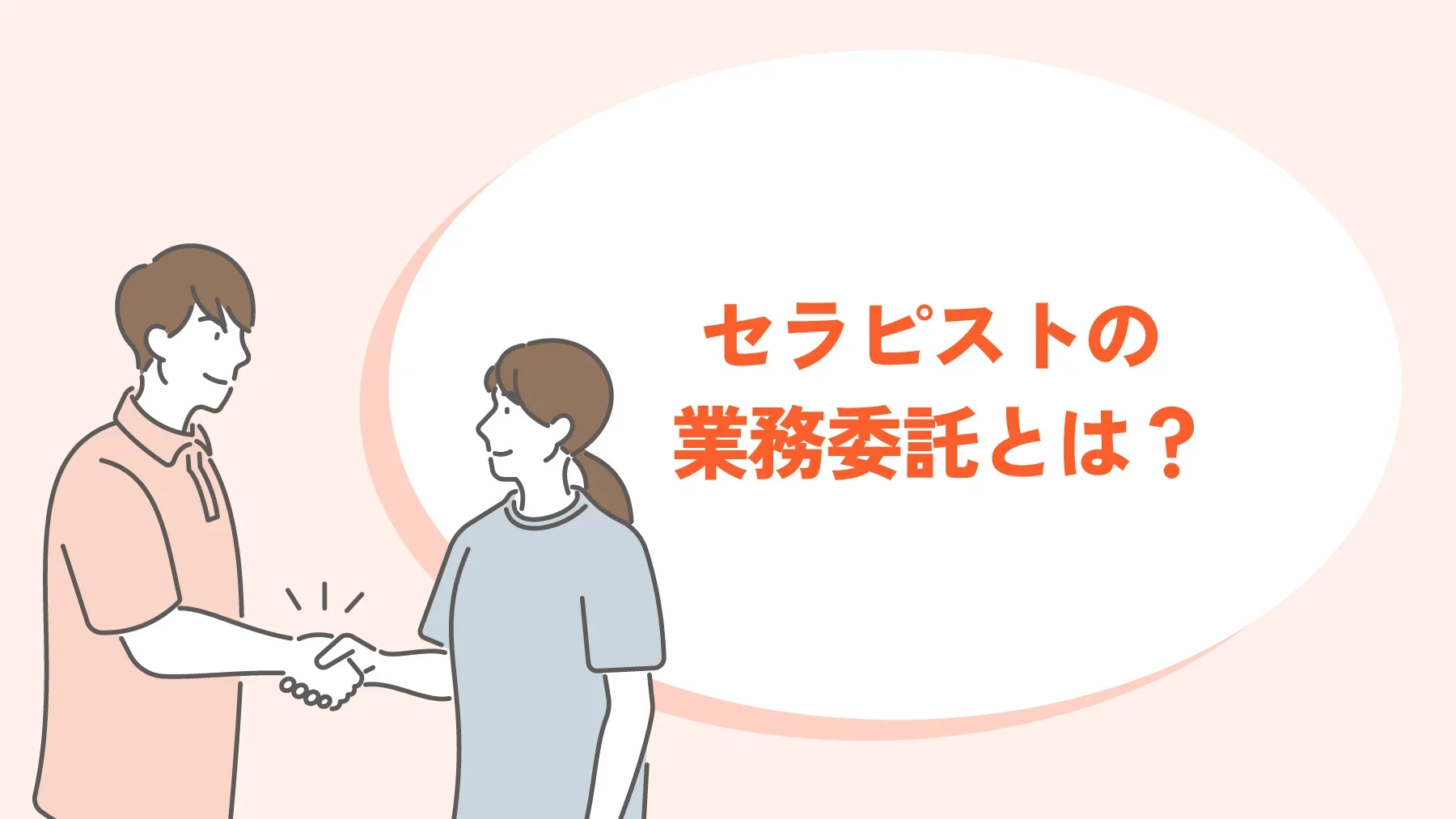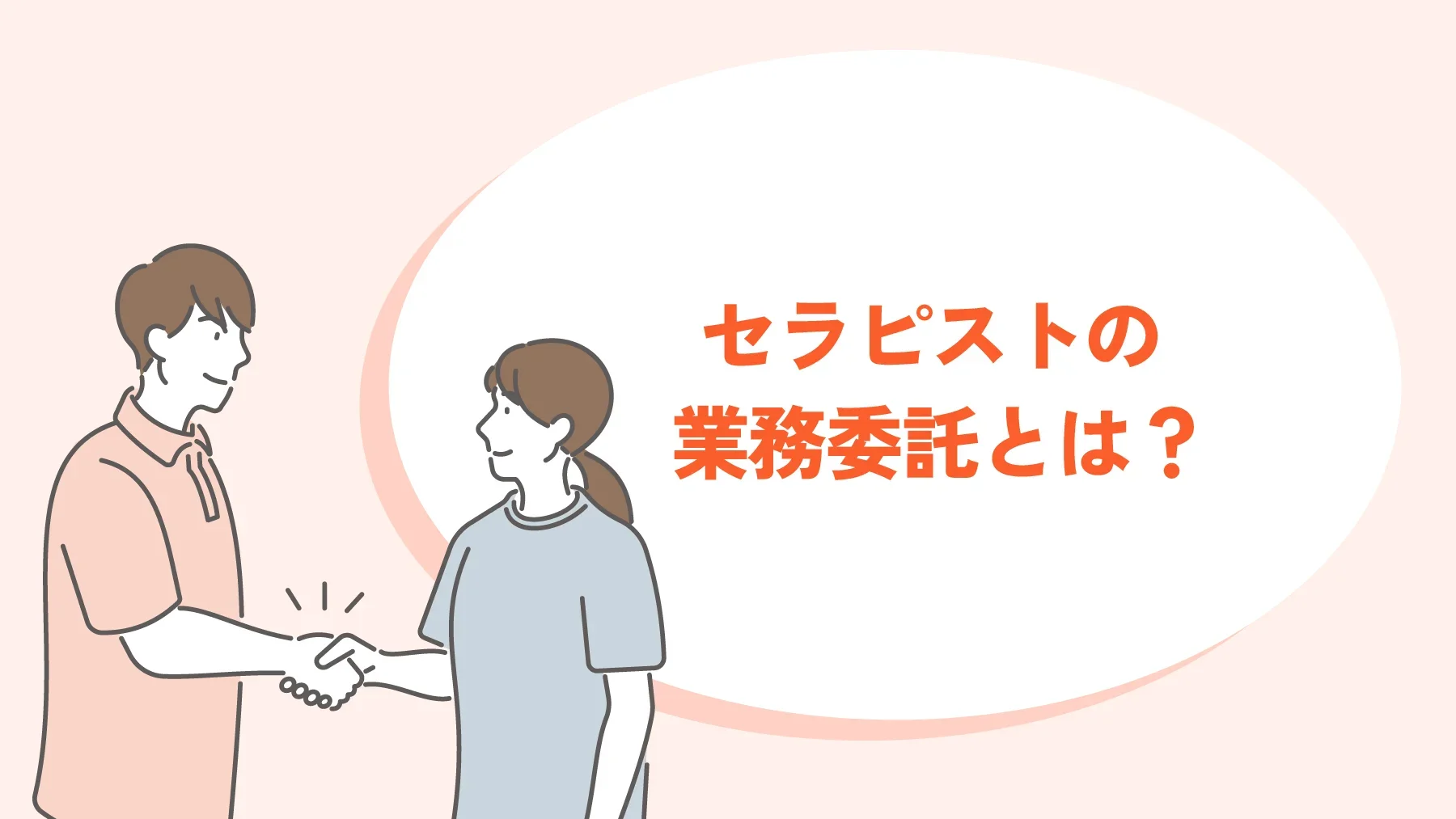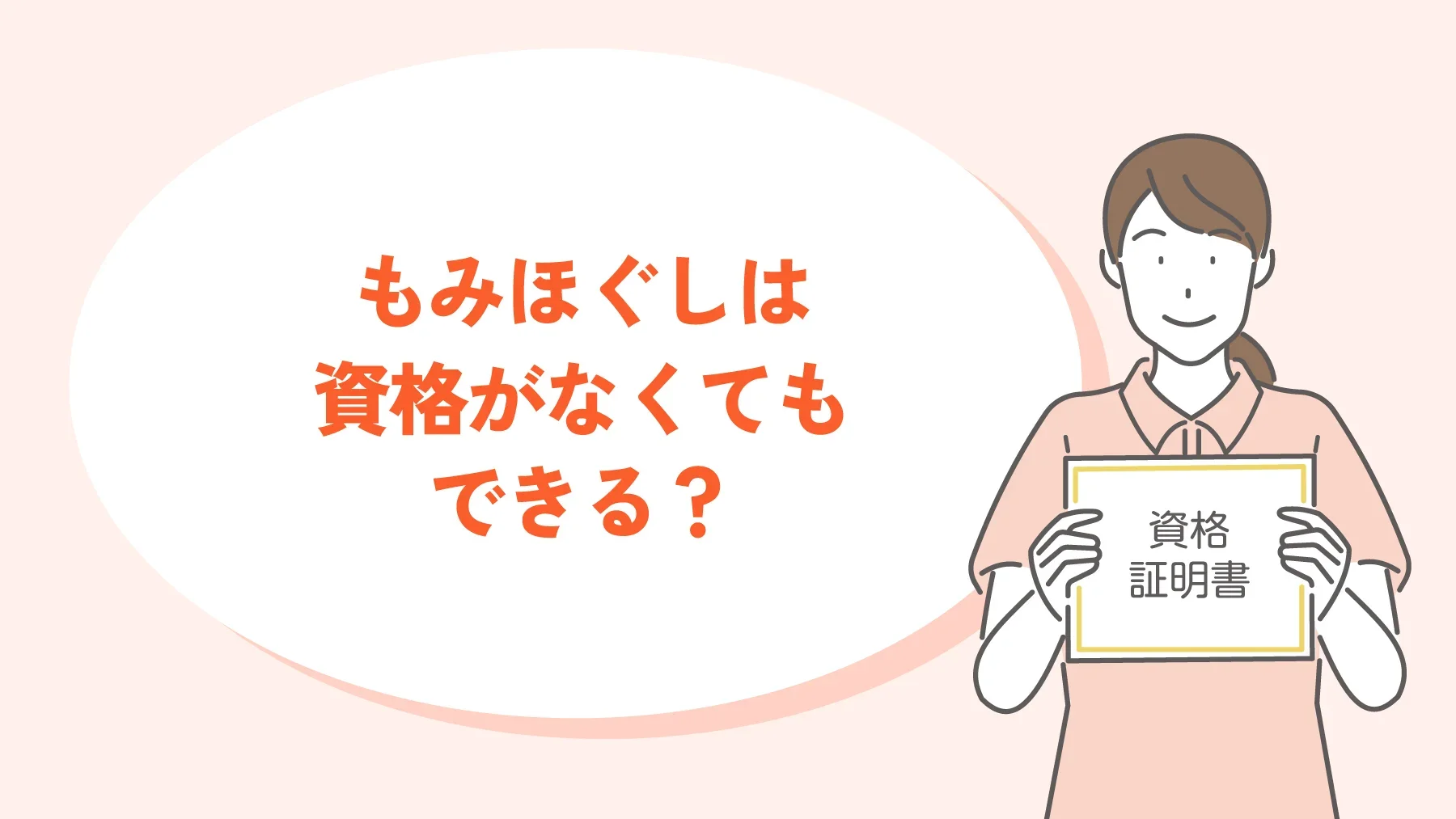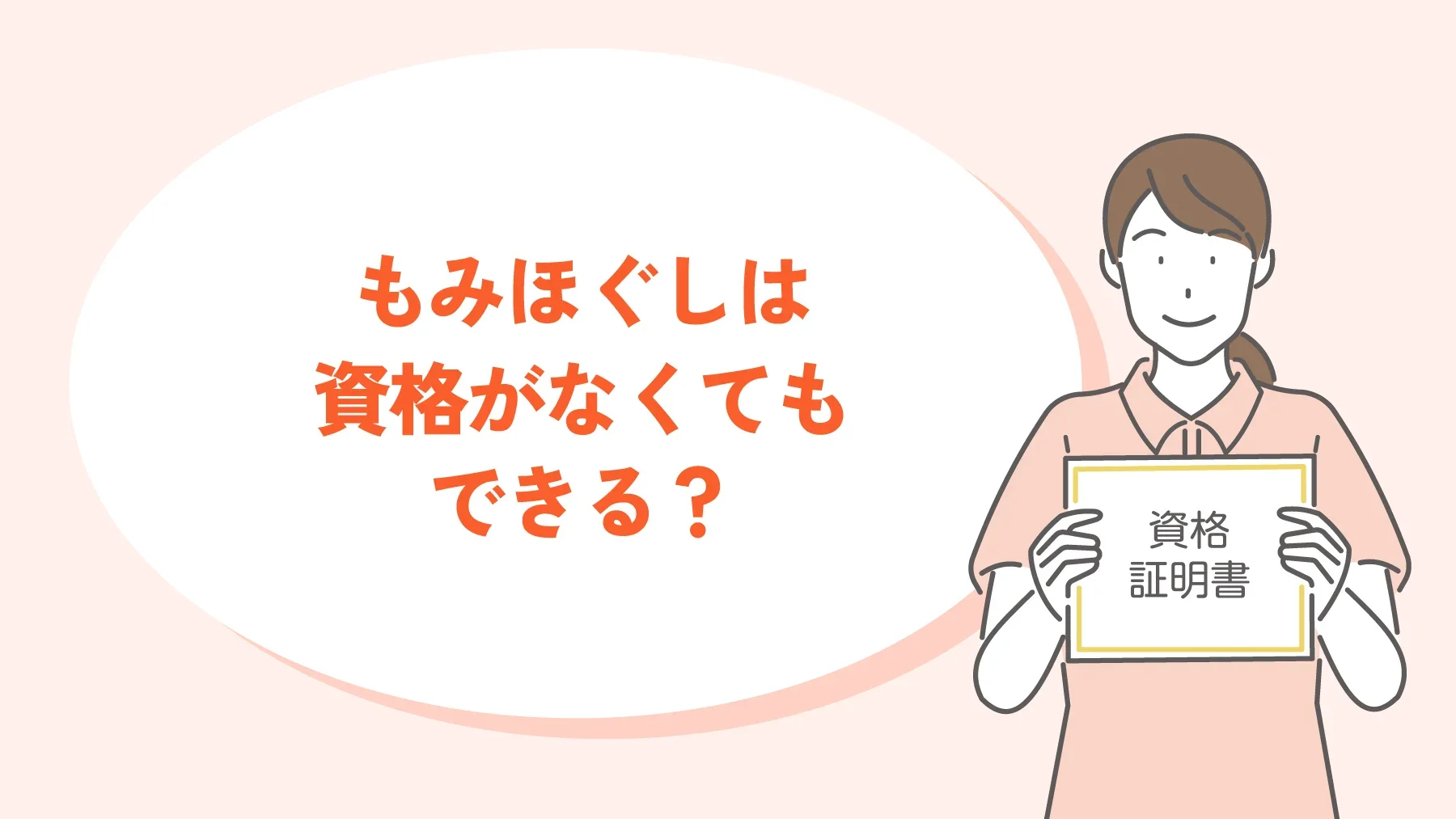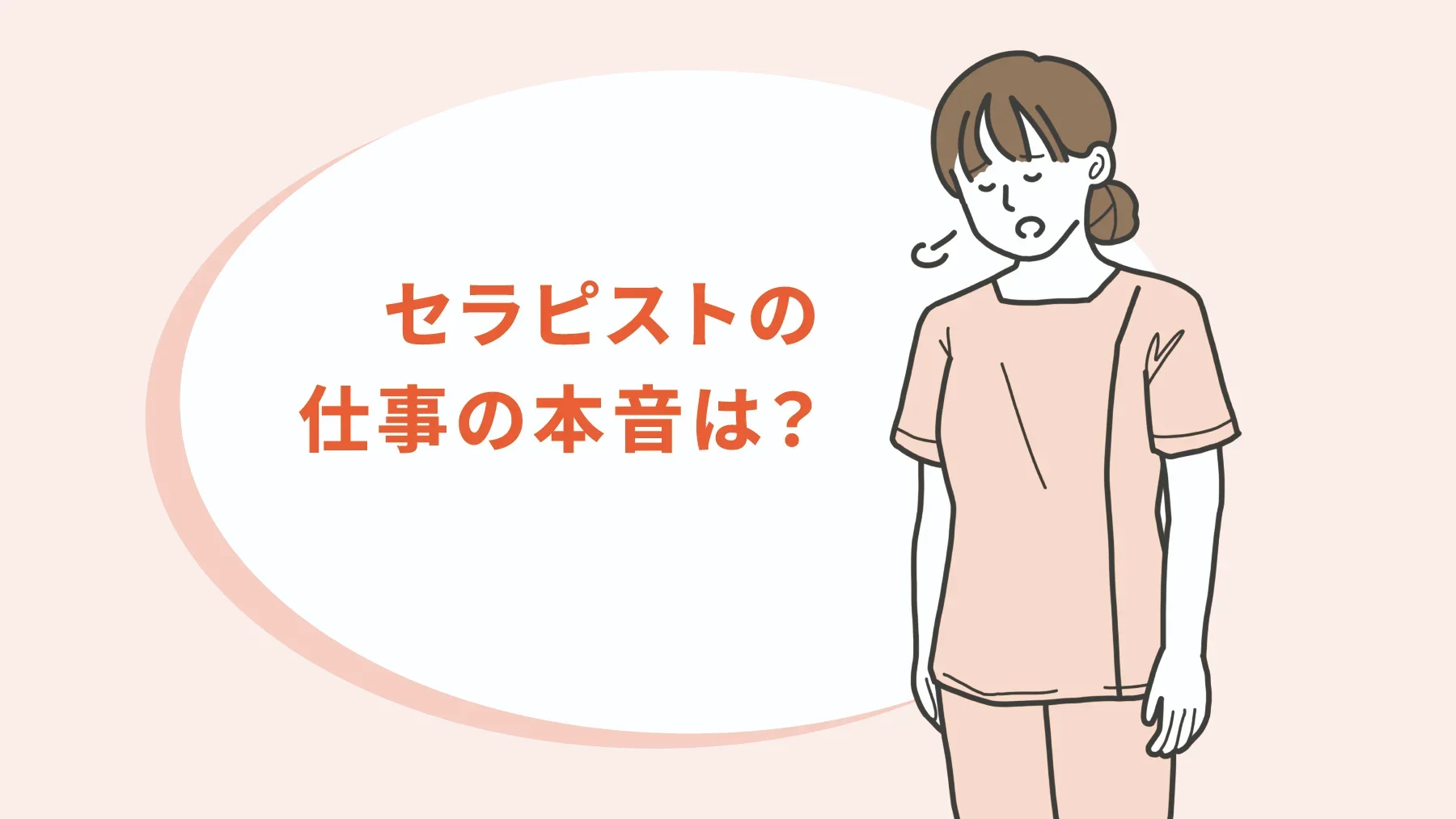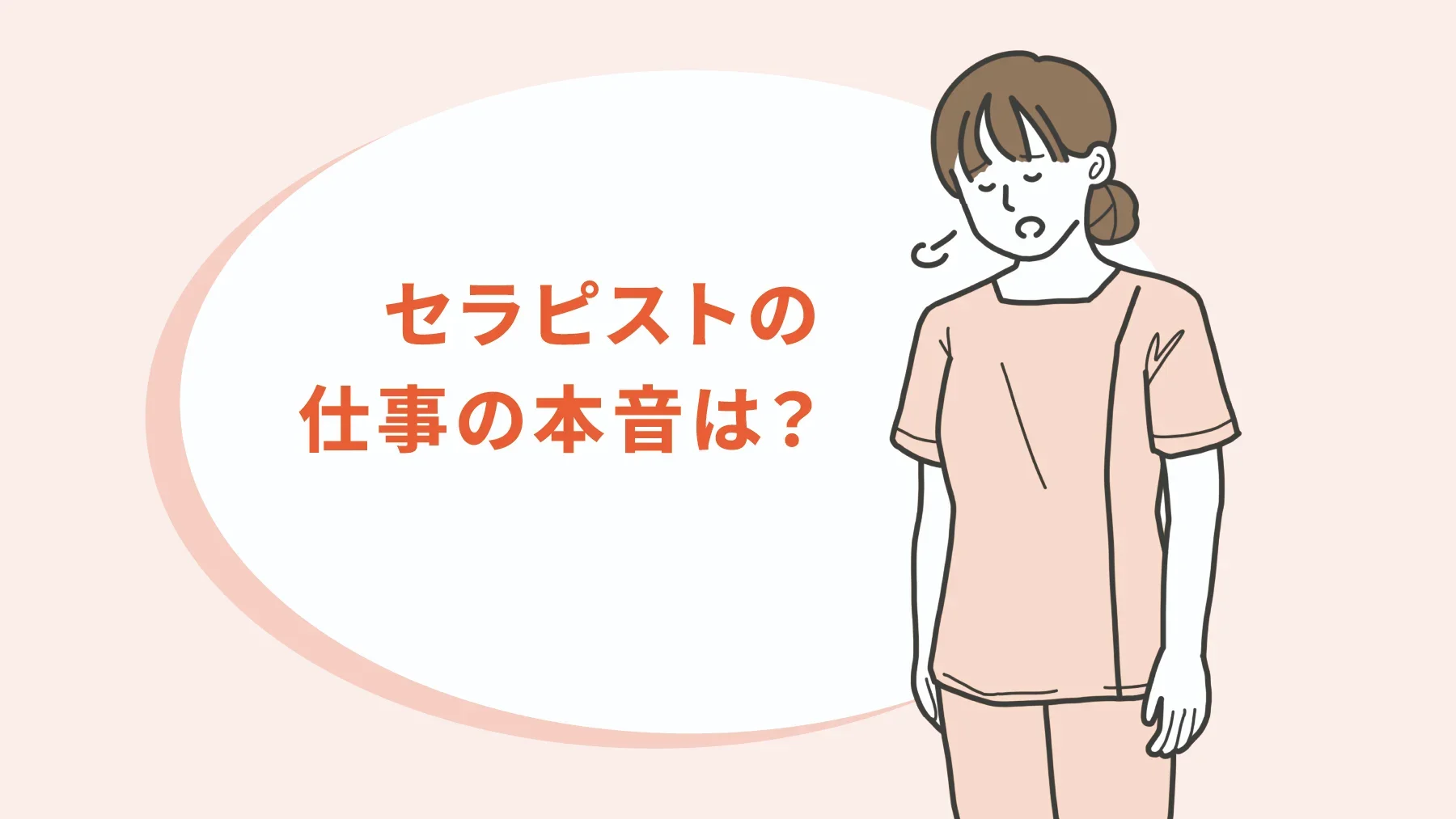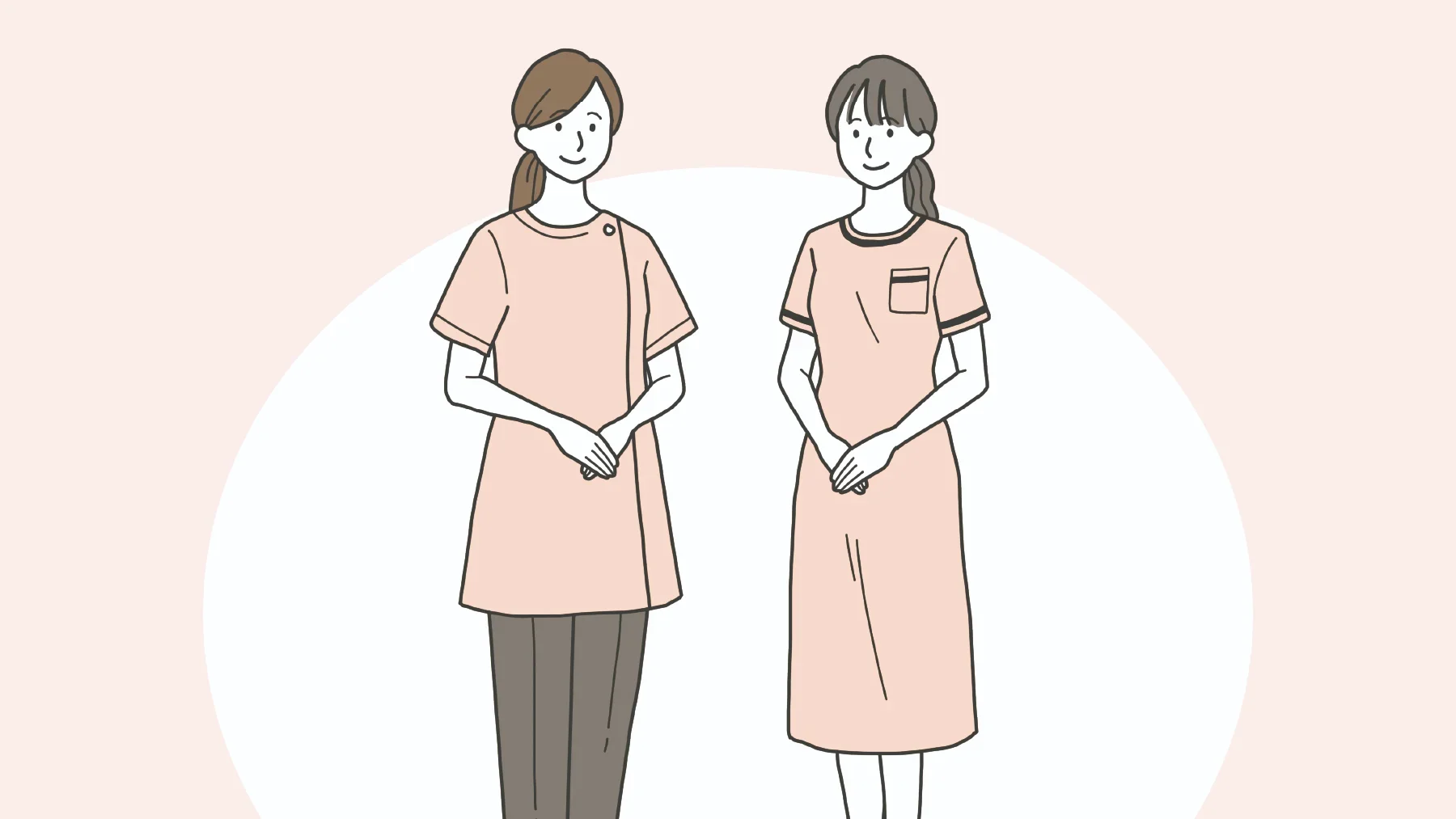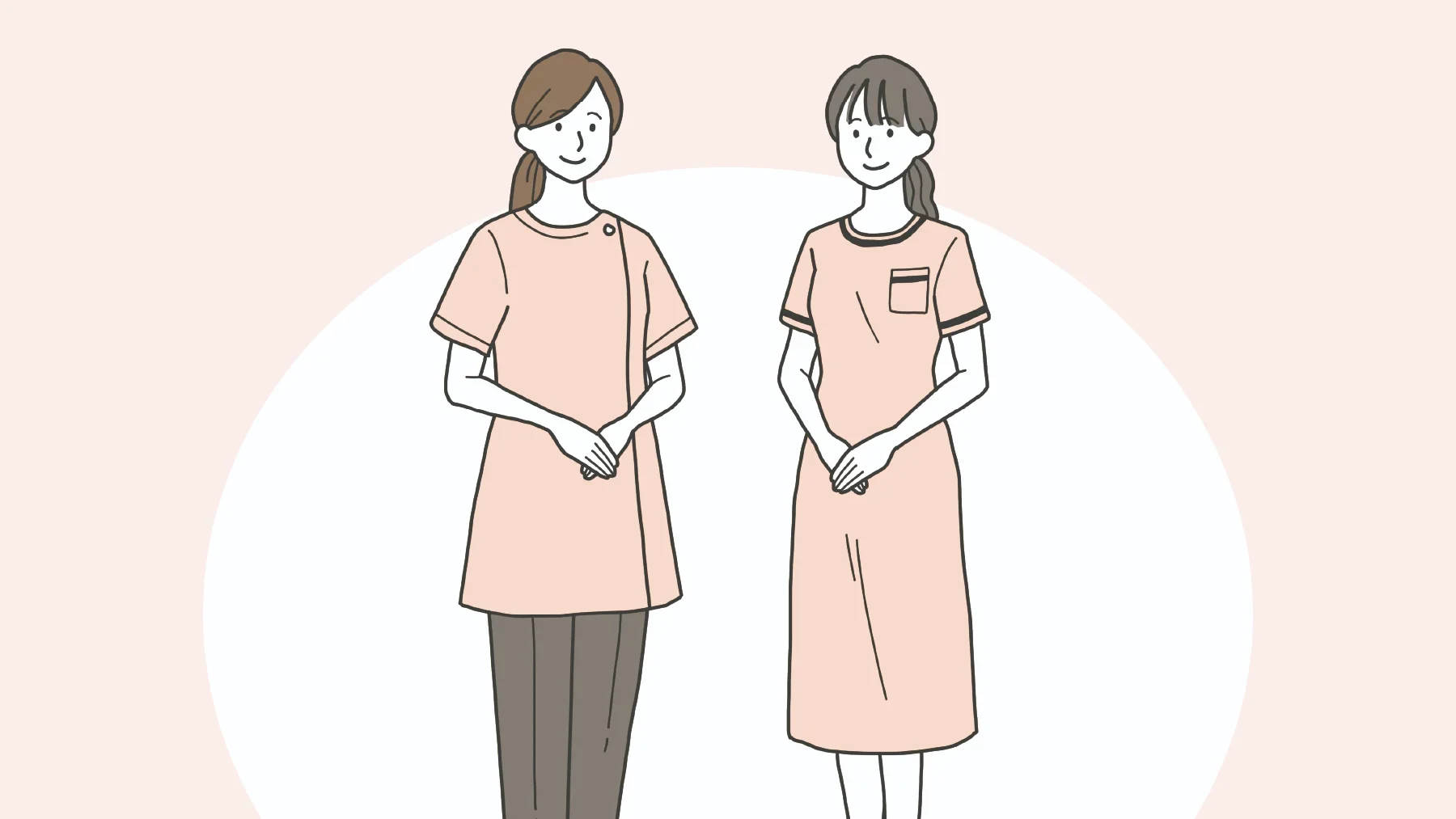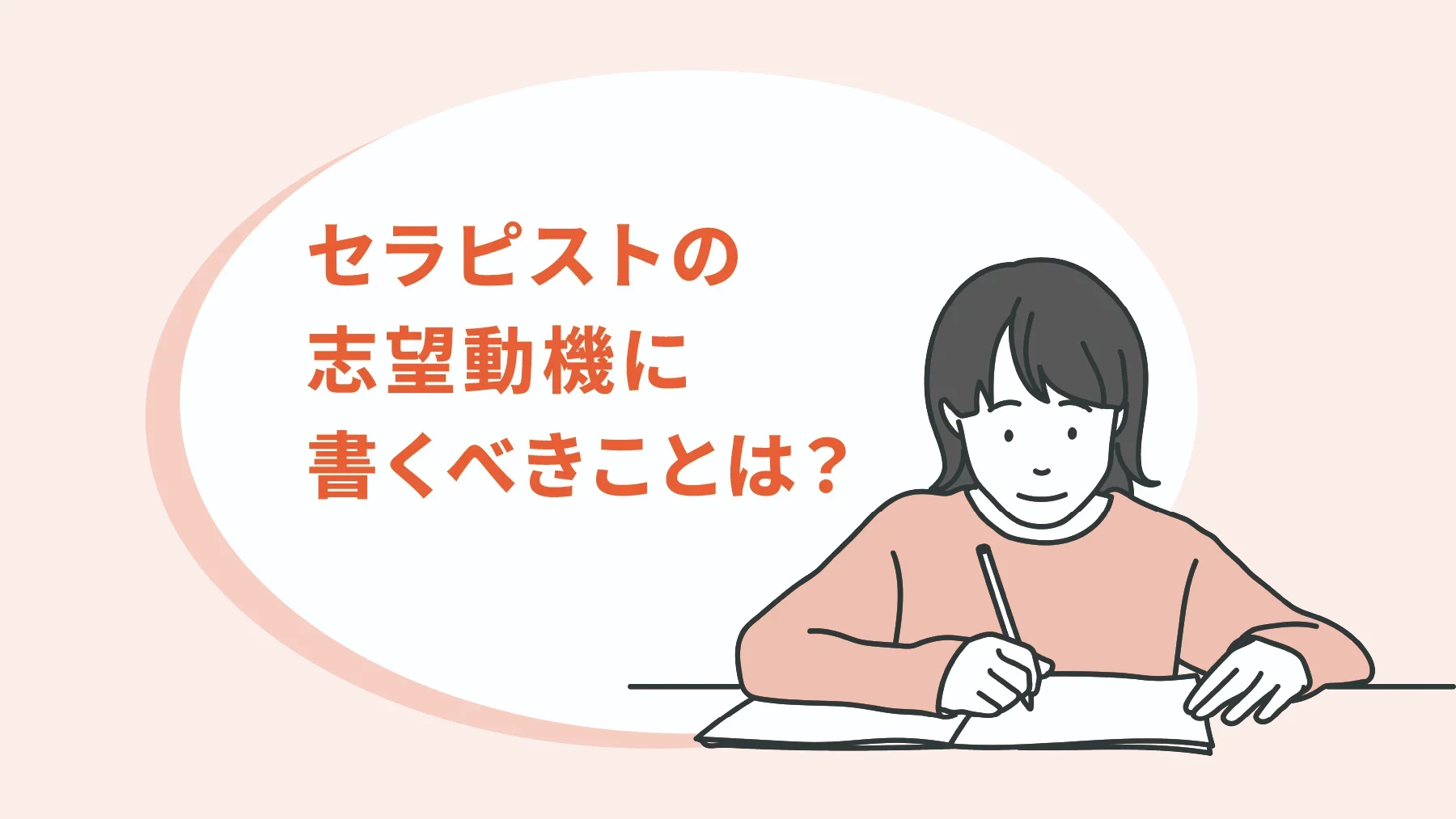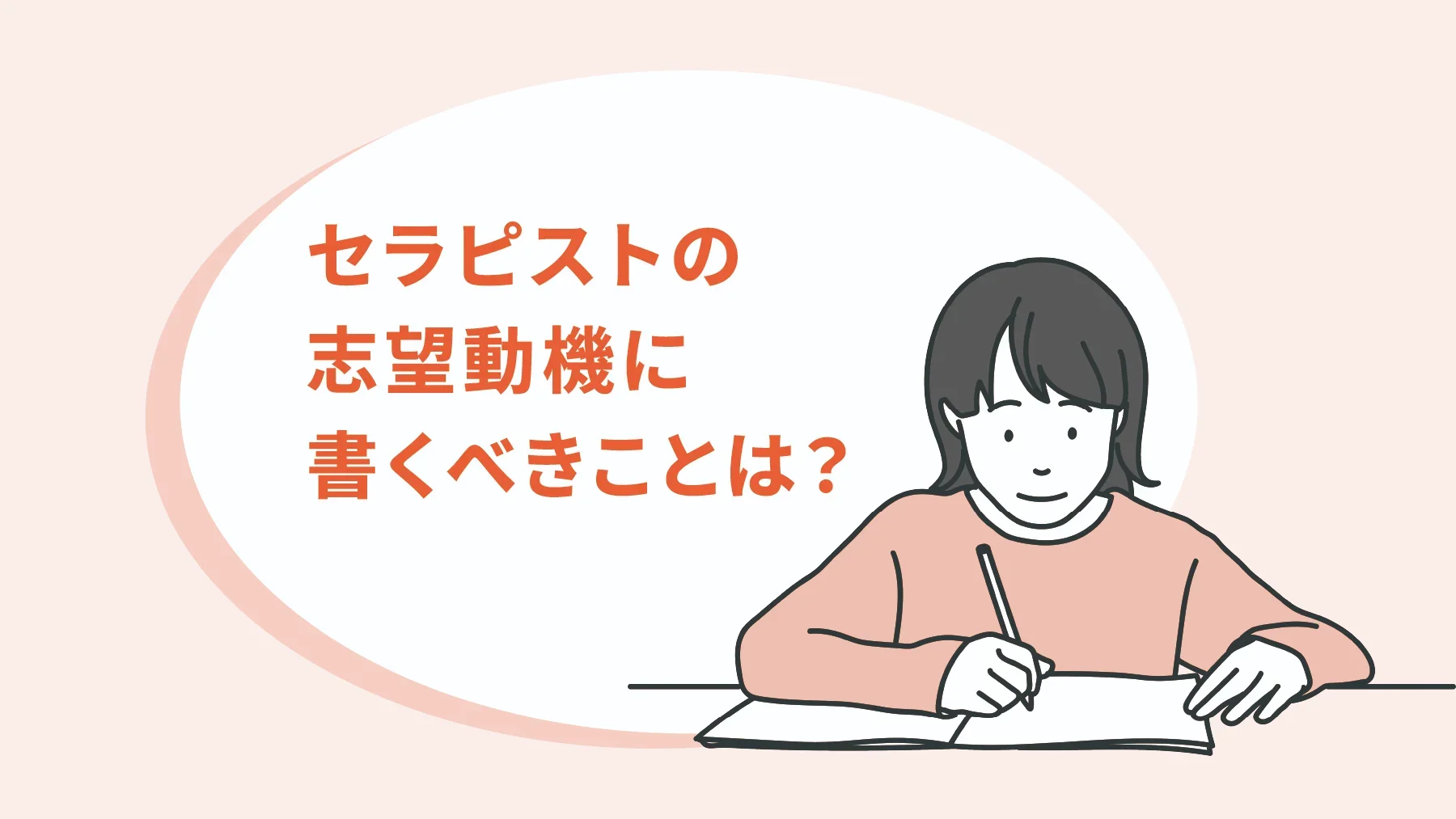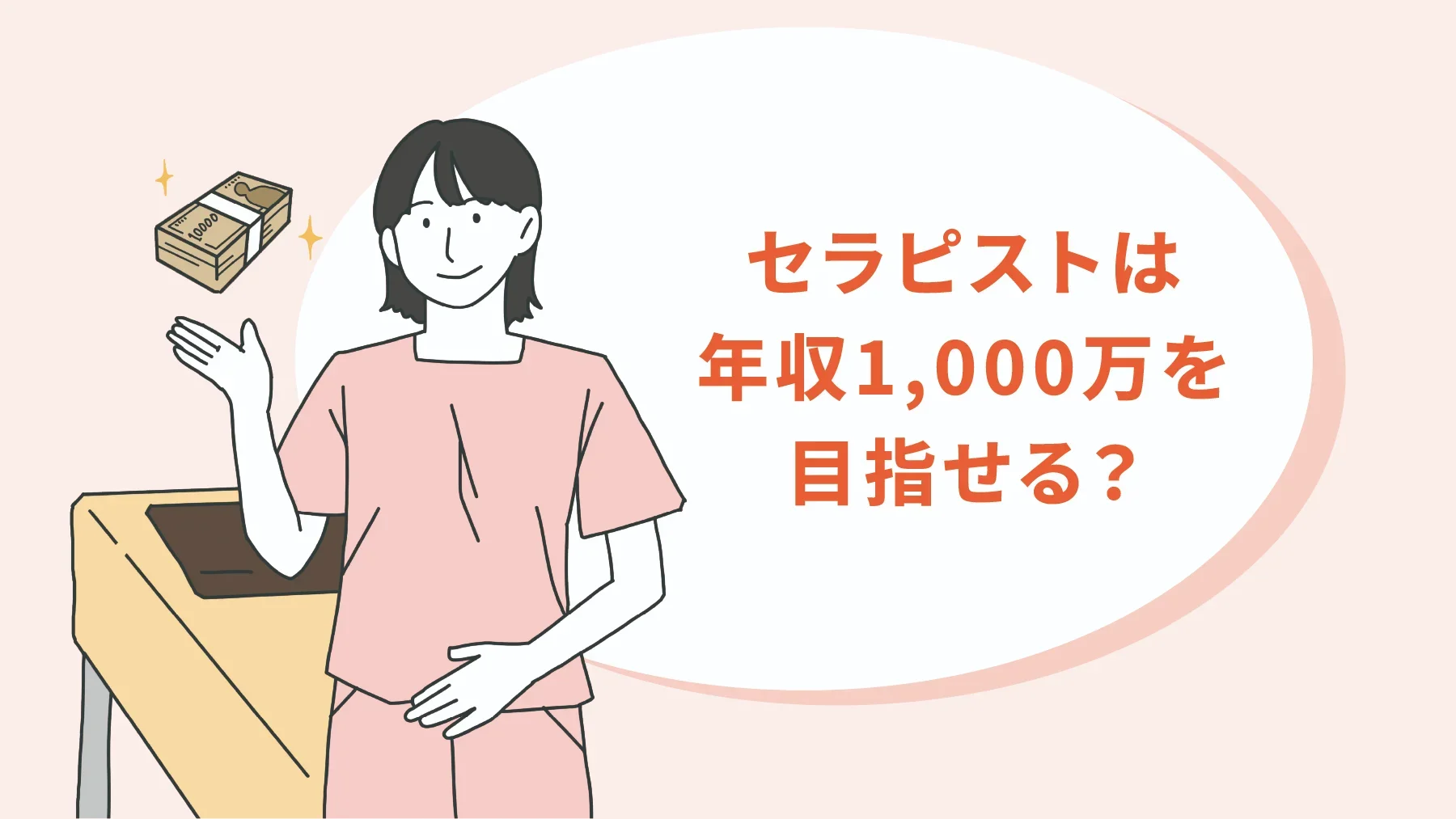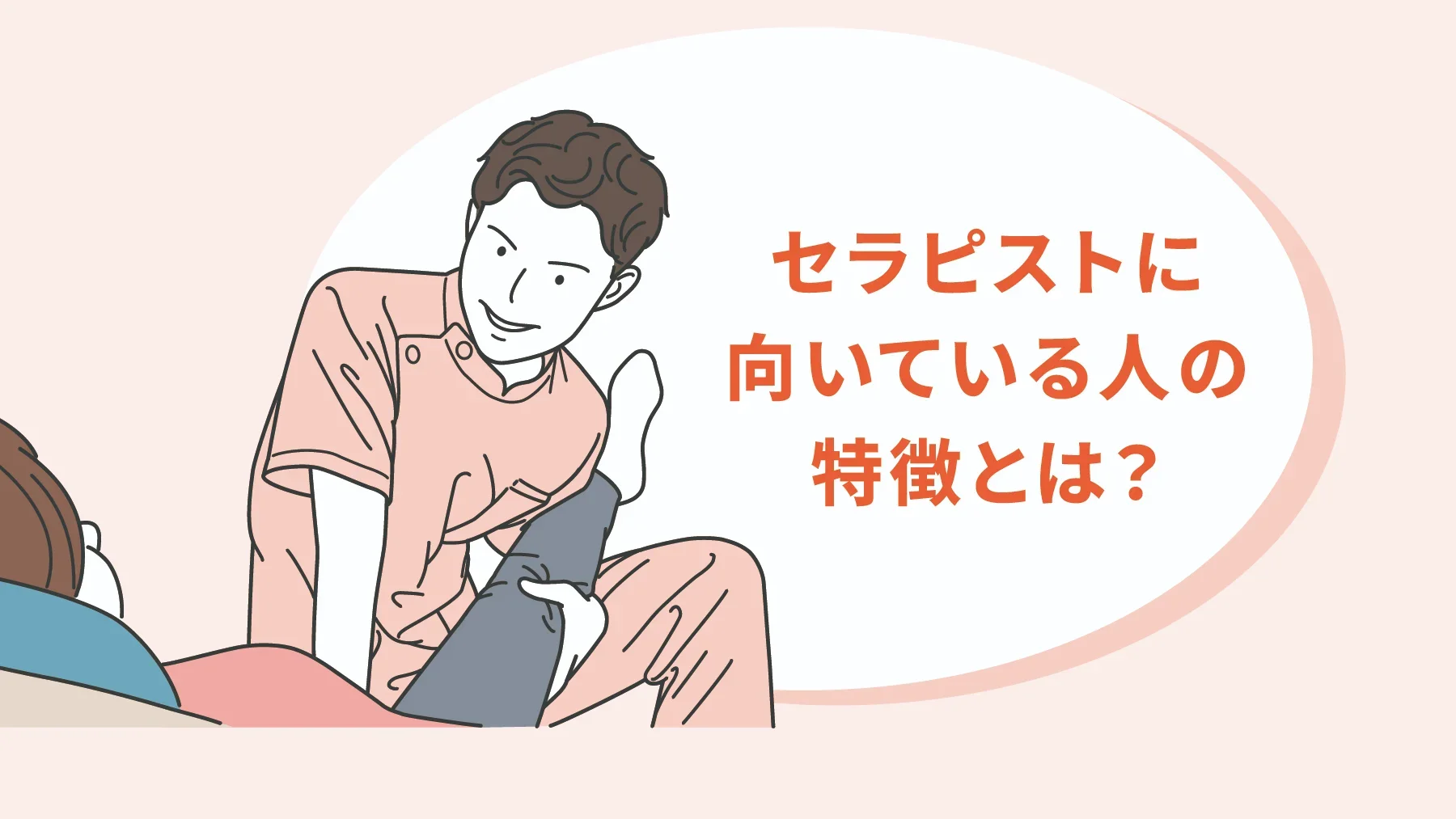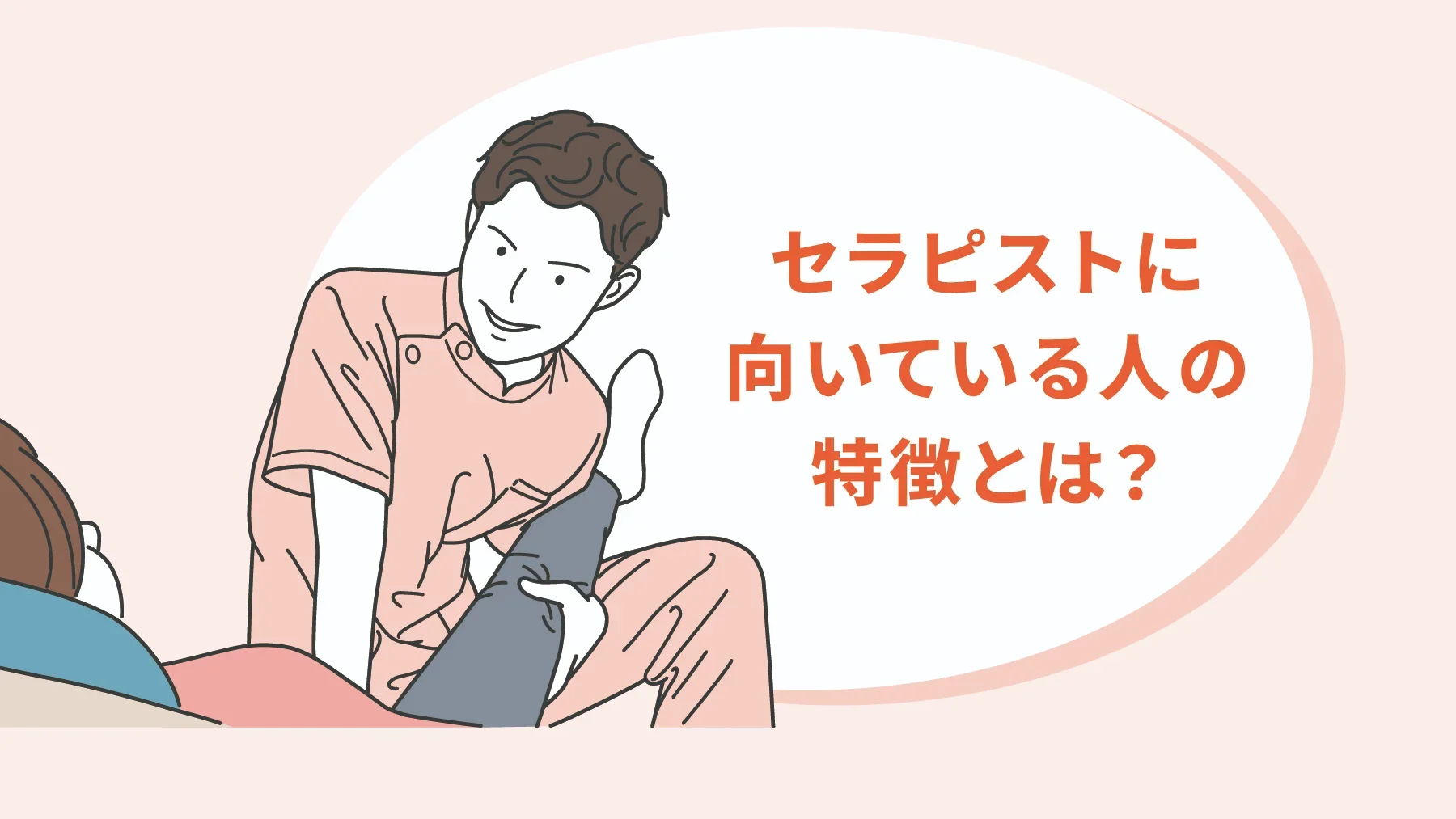-
-
これからセラピストとして働こうと思っている方のなかには、「施術中にお客様にケガをさせてしまったらどうしよう?」「万が一に備えて保険は必要?」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
お客様の身体に直接触れる仕事である以上、どれほど注意していても、トラブルが起きる可能性をゼロにはできません。
そこで本記事では、セラピストが保険に加入すべき理由から、想定されるトラブルの事例、セラピスト向けの保険の種類や選び方までを詳しく解説します。
| 【この記事で分かること】 ・セラピストが保険に加入すべき理由 ・セラピストが保険で備えるべきトラブルの事例 ・セラピスト向けの保険を提供している団体と保険の選び方 |
セラピストが保険に加入すべき理由
セラピストの仕事はお客様の身体に直接触れるため、どれだけ気をつけていても、予期せぬトラブルが発生する可能性があります。
トラブルの内容によっては高額な損害賠償を請求されるケースもあるので、万が一の事態に備え、セラピスト向けの保険に加入しておきましょう。
セラピスト向けの保険は、「賠償責任保険」が中心です。施術中にお客様をケガさせてしまったり、お客様の物を壊してしまったりして賠償責任を負った場合に、その損害や関連費用をカバーしてくれる保険です。
セラピストには、自動車の自賠責保険のような加入が義務づけられている保険は存在しません。したがってセラピストは、保険会社と提携しているリラクゼーション業界の団体に所属し、その団体を通じて保険に加入するのが一般的です。
セラピストが保険で備えるべきトラブルの事例
セラピストの仕事には、思わぬトラブルに発展するリスクが潜んでいます。例えば、以下の5つのようなトラブルが想定されます。
- 施術に関するトラブル
- 店頭販売の商品に関するトラブル
- 預かり品の盗難や紛失に関するトラブル
- 施設・設備に関するトラブル
- 無資格・無許可など法律に関するトラブル
上記はいずれも、セラピストが保険で備えるべきトラブルの事例です。どのようなリスクがあるのかを把握し、万が一に備えましょう。
施術に関するトラブル
セラピストの仕事でまず注意すべきリスクが、施術に関するトラブルです。具体的には、もみほぐしで関節に無理な負荷をかけて捻挫させてしまったり、整体やストレッチで骨折させてしまったりする事故が挙げられます。
痩身エステや脱毛施術で熱を発する美容機器を使用する場合は、誤ってお客様に火傷を負わせてしまうリスクも考えられます。
店頭販売の商品に関するトラブル
サロンで販売する商品が原因で、トラブルに発展することもあります。例えば、販売した化粧品がお客様の肌に合わず肌荒れが生じたり、サプリメントや健康食品が原因でアレルギー症状や体調不良を引き起こしたりするケースです。
また、お客様に美容機器を販売・レンタルした場合、お客様が使用方法を誤って火傷や肌トラブルを起こす可能性もあります。
預かり品の盗難や紛失に関するトラブル
ロッカールームや手荷物預かりサービスを提供しているサロンでは、お客様からお預かりしたバッグや貴重品などの紛失、ほかのお客様の荷物との取り違えにも注意が必要です。
店舗が繁華街にある場合は、空き巣による盗難被害のリスクにも気をつけなければなりません。
また、施術中の薬品類や機器の扱い方、施術の仕方によっては、お客様の服や持ち物を汚したり、傷つけたりするおそれもあります。
施設・設備に関するトラブル
サロンの施設や設備が原因で、お客様や店舗に被害を与えてしまう可能性もあります。
想定されるケースとしては、店舗の看板や照明器具が落下してお客様や通行人にケガをさせる、店内に設置している棚や装飾品が倒れてお客様に当たるなどがあります。
また、スチーマーやアロマキャンドルといった高温になる機器や火を使用する施術を行うサロンでは、火災のリスクもあります。このほか、水回り設備が故障し、漏水や配管のつまりなどが発生するケースも想定されます。
賃貸物件で営業していてこれらのトラブルが起こった場合は、原状回復義務を負う可能性がある点も留意しておきましょう。
無資格・無許可など法律に関するトラブル
提供するサービスによっては、法律で定められた資格や許可が必要です。
美容師免許を持たずにまつ毛パーマ・エクステの施術を行ったり、はり師・きゅう師の資格がないのに鍼やお灸を使ったりするのは違法行為にあたり、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
さらに、無資格で行った施術が原因でお客様に健康被害を与えてしまった場合は保険の補償対象外となり、保険金が支払われない点にも注意しましょう。
セラピスト向けの保険を提供している団体
予期せぬトラブルに備える方法の1つに、業界団体を通じて加入できるセラピスト向けの保険制度があります。
セラピスト向けの保険は、施術中の事故から施設の管理不行き届きによる事故まで、幅広くカバーしているものが少なくありません。
ここからは、セラピスト向けの保険を提供している団体を7つ紹介します。それぞれの特徴や補償内容を詳しく見ていきましょう。
手技セラピスト協会
| 年会費(会員費) | 主な補償内容 | 補償金額(限度額) | 免責金額 |
| 14,000円/年 | 施術中の事故、 施設内の事故、 販売商品や預かり品に起因する事故などを包括補償 | 対人:最大5,000万円/1名1事故 対物: 最大1,000万円/1事故 | 30,000円 |
手技セラピスト協会は、タイ古式マッサージや足つぼ、リフレクソロジー、リンパマッサージ、アロマセラピーなどの手技を行うセラピスト事業者が加入できる団体です。協会の会員になると、「手技セラピスト補償制度」が自動的に付帯されます。
手技セラピスト補償制度は、施術中の事故から施設内での事故、販売した化粧品に起因する事故、お客様から預かった物品の破損や紛失まで幅広くカバーしています。入会金は不要となっており、年会費を支払うだけで万が一のトラブルに備えられるのも特徴です。
さらに、大手損害保険会社が引き受け先となっているため補償内容の信頼性が高く、安心して事業に集中できます。
手技治療家協会
| 年会費 (会員費) | 主な補償内容 | 補償金額(限度額) | 免責金額 |
| 18,000円/年 | 施術事故・施設事故・販売物・預かり品事故、 人格権侵害まで補償 | ●対人: 最大5,000万円(1名1事故) 〇人格権侵害:最大50万円 (1名1事故) 〇施設治療費用:300万円 (1事故) ●対物: 最大1,000万円(1事故) 〇受託者賠償:最大100万円 (1事故) | 30,000円 |
手技治療家協会は、国家資格を持たない整体師やカイロプラクターなどの手技療法家を対象とした補償サービスを提供している団体です。
手技治療家協会に入会し、年会費を支払えば、施術事故や施設管理に起因する事故、販売物や預かり品に関するトラブルまで、多岐にわたるリスクをカバーできます。入会にあたって資格の有無が問われないため、学生でも加入が可能です。
補償内容には、施術に関するクレームだけでなく、名誉毀損やプライバシー侵害に対する補償も含まれています。また、事故発生時に専門家による事故対応サポートを受けられるほか、開業や業務に関するアドバイスを受けられます。
日本治療協会
| 会員種別(年会費) | 補償内容 | 補償金額(限度額) | 免責金額 |
国家資格者 民間資格者 | 手技行為に起因する賠償責任(施術中の事故)および 施設に起因する賠償責任(設備・管理上の事故)を補償 | 正会員A・B: 準会員 (各1事故あたりの金額) | 正会員A・準会員: 正会員B: |
日本治療協会は、接骨院や鍼灸院、あん摩マッサージ指圧師による訪問マッサージ、リラクゼーション、エステ、カイロプラクティックなど、施術家全般を対象とする団体です。
会員向けに「会員保障制度」を提供しており、施術行為に起因する賠償事故と、施設の設備や管理上の不備による賠償事故の両方に対応しています。
日本治療協会は、日本国内で業務を行う個人であれば、国家資格者でも民間資格者でも加入できます。ただし、会員の種別や保有資格によって、年会費や補償される限度額、免責金額が異なるため、自身の資格や必要な補償レベルに合わせてプランを選びましょう。
また、別途申し込みをして追加料金を支払えば、病気やケガで働けなくなった際の収入を補う「所得補償保険」にも加入できます。
国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会
| 年会費(保険料) | 主な補償内容・金額 | 免責金額 | 支援内容 |
ICHA認定者・国家資格者: 一般資格者:15,000円/年 | 対人・対物: 初期対応費用: 訴訟対応費用: 人格権損害担保: | ICHA認定者・国家資格者: 一般資格者:10,000円 | 示談交渉に関する相談・アドバイスが受けられる (※示談交渉そのものは本人または弁護士が対応) |
国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会(ICHA)は、高齢化社会の進展を見据え、コメディカル分野(医療周辺業務)の知識・技術向上を支援する団体です。
会員を対象に「施術者補償制度」を設けており、団体が認定する資格を持つ施術者や国家資格者、民間資格を持つ施術者が加入できます。
施術者補償制度は、会員費の入金が確認された翌日から補償が開始されます。万一の事故の際には、示談交渉に関する相談やアドバイスを受けられるため、セラピストにとって心強い制度といえるでしょう。
日本全身美容協会
| 年間保険料(掛金) | 補償内容 | 補償限度額(目安) | 免責 |
| 30,000円/年 (1店舗あたり) | エステサロン施術業務および施設設備に起因する 対人・対物事故の賠償責任を補償 | 対人: 対物: | 1回の事故につき20,000円の自己負担 |
日本全身美容協会(JTBA)は、エステティックサロン業界の健全経営と業界発展をめざす団体です。
会員向けの総合保険制度「サロン賠償補償制度」を提供しており、制度を利用するには、日本全身美容協会への入会が必要です。
サロン賠償補償制度は、施術中のミスなどでお客様を負傷させたり、お客様の私物を壊したりした場合に生じる法律上の賠償金などを補填するための保険です。
オプションとして、販売している商品の欠陥が原因で発生した事故をカバーする「PL(生産物賠償責任)保険」も用意されています。
日本医療・美容研究協会
| 年会費 | 補償内容 | 補償限度額 (基本プラン) | 補償限度額 (火災補償) |
脱毛ありプラン: 脱毛なしプラン: | 施設賠償責任+生産物賠償責任+受託者賠償責任をセットにした包括保険 ※オプションで火災補償も追加可能 | エステ行為での対人: エステ行為での対物: エステ行為以外での対人・対物: 初期対応費・施設治療費: 人格権侵害: 生産物賠償: 受託者賠償: | 商品・什器の損害・休業損失・営業継続費用: 借家人賠償保険:
|
日本医療・美容研究協会(JMB)は、美容業界に特化したリスクマネジメント専門団体です。会員向けに「JMB保険制度」を用意しています。
JMB保険制度は、エステサロンで発生しやすい事故を包括的にカバーする保険です。施設賠償、生産物賠償、受託者賠償がセットになっており、販売商品や預かり品に関するトラブルにも対応します。
さらに、お客様の肌トラブルに対する提携クリニックの紹介や、弁護士による初期対応のアドバイスなど、専門家によるリスクコンサルティングも行われるのが特徴です。
日本リラクゼーション業協会
| 年間保険料 | 補償内容 | 補償限度額 | 免責金額 |
| 1,350円~1,800円/年 (1人あたり) | 施設所有(管理)者賠償責任保険 + 生産物賠償責任保険 + 受託者賠償責任保険 | 対人・対物: 1事故につき最大1,000万円~1億円 | 0円 |
日本リラクゼーション業協会は、リラクゼーション業界の健全な発展と、サービスの質の向上をめざして設立された団体です。
会員向けに「リラクゼーション業補償制度」を設けており、店舗オーナーから現場で働くセラピストまで、事業に関わる人々を包括的にサポートしています。
リラクゼーション業補償制度は、施術中・施術後のトラブル、店舗内での事故、販売品による健康被害、預かり品の紛失・破損事故など、あらゆるトラブルに対応しています。被害者への対応費用や訴訟対応費用、人格権侵害に関する賠償も補償範囲です。
協会の顧問弁護士や医師、社労士などの専門家に、事故やクレーム対応について相談できる体制も整っています。
セラピスト向けの保険を選ぶ際のポイント
.webp)
セラピスト向けの保険はさまざまな団体から提供されており、補償内容や保険料も多岐にわたります。自身の働き方や事業規模、将来の展望まで見据えたうえで、適切な保険を選びましょう。
以下では、セラピストが保険を選ぶ際に注意すべき3つのポイントを解説します。
働き方や業務内容に合った内容か確認する
保険を選ぶ際は、自身の働き方やサービス内容にマッチしているか確認しましょう。
例えば、業務委託契約を結んでサロンの一角を借りて施術を行う場合、自分で施設を所有・運営していないため、施設賠償責任の補償は不要かもしれません。この点は施設所有者(管理者)に確認しておくことが大切です。
出張して施術を行う場合は、訪問先での施術事故にも対応できる保険を選ぶと安心です。
また、保険によっては、特定の資格を持っていないと、一部補償を受けられないケースがあります。加入前に、必要とする補償がきちんとカバーされるかをチェックしましょう。
従業員数やサロンの規模に合っているか考慮する
サロンの規模や従業員の数によって、直面するリスクの種類や発生頻度は異なります。個人で運営している自宅サロンと、複数のセラピストと契約している大型サロンでは、必要となる保険の種類や補償金額も異なるでしょう。
また、将来的にセラピストと契約して事業を拡大したり、新しい施術メニューを追加したりする予定がある場合は、補償範囲を調整できる保険を選んでおくことが重要です。
複数の保険会社を比較する
セラピスト向けの保険を検討する際は、複数の保険商品を比較・検討しましょう。各保険の補償範囲、補償される金額の上限、年間の保険料、付帯サービスなどを一覧にして比べてみると、各社の強みや特徴が分かります。
あわせて、想定されるリスクに対して十分な補償額が設定されているか、保険料を無理なく支払い続けられるかも見極めましょう。
補償内容が似ている保険が複数ある場合は、保険金請求を経験した人の声や、加入者の満足度などを調べておくと、いざというときに安心して任せられる保険かどうか判断しやすくなります。
セラピストの保険に関するよくある疑問
保険への加入を検討する際にはさまざまな疑問が浮かぶものです。そこで以下では、セラピストの保険に関してよくある質問と回答をまとめました。保険選びの参考にしてください。
セラピストは個人で保険に加入できる?
個人で活動しているセラピストは、リラクゼーション業界の団体の会員となり、その団体が提供している保険に加入するのが一般的です。
例えば以下の団体では、フリーランスのセラピストや自宅サロンの経営者、業務委託契約で働く方などの加入を受け付けています。
- 手技セラピスト協会
- 手技治療家協会
- 日本治療協会
- 国際コ・メディカルアンドヘルスケア協会
- 日本全身美容協会
- 日本医療・美容研究協会
- 日本リラクゼーション業協会
上記の団体に入会して所定の会費や保険料を支払えば、団体が契約している保険会社の賠償責任保険に加入でき、万が一の際に補償を受けられます。
セラピストの保険料は経費にできる?
個人事業主として活動しているセラピストが支払った保険料は、確定申告の際に経費として計上できます。セラピスト向けの賠償責任保険は、事業を安全に遂行するうえで必要な支出とみなされるためです。
ただし、経費として計上できるのは、あくまで事業活動に関連する保険に限られます。プライベート用の保険料は経費として計上できません。
セラピストが業務委託で働く場合保険への加入は必要?
業務委託契約で働くセラピストも、保険に加入しておくとよいでしょう。
業務委託の場合、施術中にお客様とのあいだでトラブルが発生して損害賠償を求められることがあっても、請求先は施術を行った店舗になる可能性があります。
しかし、サロン側には個人事業主であるセラピストを守る義務はなく、施術を担当したセラピスト本人が最終的に賠償責任を負うケースもあり得ます。
したがって、自分自身を守るためにも、個人で賠償責任保険に加入しておくと安心です。
>セラピストの業務委託とは?メリットやデメリット、職場の選び方も解説
まとめ
セラピストとしてお客様に最高のサービスを提供し、安心して自身のキャリアを築いていくためには、保険への加入が欠かせません。ていねいに施術を行っていても、施術中のケガや施設内での事故など、予期せぬ事態が起こる可能性はゼロではないからです。
適切な保険に加入していれば、高額な賠償責任が発生した際の金銭的なダメージを軽減でき、お客様からの信頼の損失も最小限に抑えられます。
一方で、セラピスト向けの保険にはさまざまな種類があるため、自身の働き方や提供するサービス内容、サロンの規模などを総合的に考慮してプランを選ぶことが重要です。
本記事で紹介した選び方のポイントや各団体の特徴を参考にして自分にぴったりの保険を見つけ、安心して仕事に専念できる環境を整えましょう。




 06-4400-5406
06-4400-5406